決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


交通事故に遭った場合、法的手続を行わないで解決するのであれば、加害者(加害者側保険会社)と交渉することで「示談」に至り、一定の示談金(補償金)を受け取るという流れが通常です(相手が保険加入している場合)。
しかし示談金(補償金)は、交通事故被害を補填するものであり、慰謝料・積極損害・消極損害など複数の損害に対する填補金です。そのため、示談金(補償金)がいくらになるかは、交通事故の内容・態様に従って決まるものであり、ケースバイケースであると言わざるを得ません。
今回は、交通事故の示談金の計算例・内訳や、示談金が増額するポイントなどについて簡単に解説します。被害者がどのような補償を受けられるのか参考となれば幸いです。
他にも交通事故で適正な示談金を獲得するために必要な知識は多数あります。
下記より、不足している知識についてもご確認頂くことをお勧めします。
|
交通事故の示談に関する知識一覧 |
目次
まずは「交通事故における示談金とはどういうものなのか」を解説します。
示談金と慰謝料を混同している方も多いかと思いますが、厳密に言うと慰謝料は示談金の一部になります。

そして、交通事故被害者らの「損害」には、交通事故により入通院を余儀なくされた場合の治療費・交通費、負傷により就労できなくなったことにより発生した休業損害、負傷して入通院を余儀なくされたことに対する精神的損害等が含まれます。
慰謝料とは、この精神的損害を賠償するためのお金を意味します。したがって、交通事故の場合の「示談金」は、慰謝料を含みつつも、慰謝料以外の損害賠償金も含むのであり、慰謝料よりも広い概念であるということがいえます。
示談金は示談が成立した場合に支払われるお金です。すなわち、被害者と加害者との間の交渉により、示談の範囲(損害賠償の範囲)について合意に至ることが前提として必要です。このような示談交渉は、相手が任意保険に加入している場合は、加害者側保険会社の担当者が対応するのが通常です。最終的な示談金の金額も当該合意の中で決定されることになります。
このように、示談金は理論的には双方合意により定まるものであり、その金額等について特に法律上の制限・ルールはありません。したがって、当事者双方で合意がしさえすれば、示談金はいくらであっても法律上は問題ありません。
しかし、示談金は上記のとおり交通事故被害の損害を賠償するお金ですから、当然、適正妥当な範囲で合意されるべきものです。そのため、もしも相手と示談するに当たっては、ケースごとに適正額を見極める必要があるでしょう。
上記のとおり、示談金を合意するに当たっては「適正額かどうか」を慎重に検討する必要があります。
しかし、示談金については明確な相場があるものではなく、事故の状況・態様に応じてケース・バイ・ケースです。しかし、示談金がカバーする各損害項目については、これを算定する一定の基準・考え方があります。
そのため、適正な示談金を算定するためには、「被害者側に生じている各損害について、適正な基準・考え方に従ってこれを算定し、これを積み重ねる」という方法に依ることとなります。
もっとも、一般人は「交通事故の損害計算に精通している」ということは通常はありませんので、いざ算定しようと思っても「いくらであれば妥当なのか」「示談金の計算方法がわからない」など、なかなかうまくいかないのが普通でしょう。このような場合は、知識・経験の豊富な弁護士にアドバイスを受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
示談金は、大きく分けると以下の3つに分類されます。ここでは各内訳について解説します。
|
積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に支払った費用を指します。主なものとしては「治療費」「交通費」「文書料」などがあり、一覧にしてまとめると以下の通りです。
<積極損害の項目一覧>
|
消極損害とは、交通事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入や、利益を得られなかったことに伴う損害を指します。
例えば、交通事故により入通院を余儀なくされたような場合、その間は十分に仕事をすることができず、賃金の支払いを受けられません。
また、仮に治療を尽くした結果何らかの後遺症が残り、これにより一定の労働能力喪失が認められるような場合は、「将来的に得られるはずの稼働による利益を失ったもの」と評価されます。このような利益の喪失に伴う損害を「消極損害」と呼びます。
なお消極損害については、休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の3つに細分化されます。
休業損害とは、交通事故による怪我の影響で、満足に仕事ができない間に発生した減収に関する損害を指します。
基本的には以下の式で賠償金額が決められますが、専業主婦や個人事業主など休業が明確でない場合には、休業日数をどのように算定するのか慎重な検討が必要です。
また、あまりないケースですが「会社から証明を受けた休業日数について、因果関係の観点から疑義が生じる」ということもあり得ます。もし、休業日数の考え方や基礎収入の考え方で相手方と認識が異なる場合、この点について協議による妥結を目指して交渉していくことになります。
<計算式>
|
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
後遺障害逸失利益とは、交通事故で負傷し、治療を尽くしても後遺症が残ったような場合に、当該後遺症の影響で労働能力の全部又は一部を失い、将来的に得られたはずの収入が得られなくなったことに伴う損害を指します。
計算方法としては以下の通りですが、すべてを解説するのは複雑なため、詳細については「逸失利益の計算方法|正当な損害賠償を請求するための基礎知識」にてご確認いただければと思います。
<計算式>
|
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡した際、交通事故に遭わずに生存していれば、就労により獲得できていたはずの収入が得られなくなったことに伴う損害を指します。
計算方法としては以下の通りですが、こちらもすべてを解説するのは複雑なため、詳細は「逸失利益の計算方法|正当な損害賠償を請求するための基礎知識」にてご確認いただければと思います。
<計算式>
|
死亡逸失利益=(基礎収入―生活費控除率)×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数 |
※生活費控除率:将来獲得できたであろう収入から、支出するはずだった生活費を控除する際に用いる数値
慰謝料とは、被害者とその家族が負った精神的苦痛への補償を指します。
慰謝料は被害の程度によって、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に細分化されます。ここでは、それぞれの慰謝料について解説します。
なお「交通事故の示談金の基礎知識」でも解説した通り、示談金そのものはケースに応じて金額が大きく異なるため、特に相場のようなものはありません。他方、示談金の一部を構成する慰謝料については、他の損害項目と同様に一定の算定基準があります。
|
計算基準 |
概要 |
請求できる慰謝料額 |
|
自賠責基準 |
自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準 |
最も低い |
|
任意保険基準 |
加害者が任意加入する保険会社の内部で定められた算定基準 |
自賠責基準より多少高い程度 (※保険会社によって異なります) |
|
弁護士基準 |
裁判所の先例を踏まえた算定基準 |
最も高い |
なお任意保険基準については、保険会社によって設定している基準値が異なりますので、以下で紹介する相場額は目安の一つとしてとどめておいてください。
また弁護士基準で示談交渉する場合、ほかと比べて高額な慰謝料を請求できますが、弁護士が介入しない事件では、相手保険会社は弁護士基準で慰謝料を算定することに難色を示す傾向にあるようです。そのため、弁護士基準での請求を希望するのであれば、当初から弁護士の力を借りた方が良いかもしれません。
【関連記事】交通事故の慰謝料相場|妥当な慰謝料を獲得するための全知識
入通院慰謝料とは、入通院などの怪我の治療にかかる精神的苦痛への補償を指します。
以下のように、入院期間・通院期間・ケガの程度などを踏まえて慰謝料額を算定することになります。
<自賠責基準の計算方法> ※①・②のうち計算結果の小さい方が適用
|
<任意保険基準の相場表(目安)>


後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我について治療を尽くしたものの一定の後遺症が残り、当該後遺症について一定の労働能力喪失が認められるもの(後遺障害)に対する精神的苦痛への補償を指します。
以下のように症状の程度によって14段階の等級が定められており、1級が最も高額に設定されています。
<後遺障害慰謝料の相場表>
|
等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準(目安) |
弁護士基準 |
|
1,100万円 |
1,300万円 |
2,800万円 |
|
|
958万円 |
1,120万円 |
2,400万円 |
|
|
829万円 |
950万円 |
2,000万円 |
|
|
712万円 |
800万円 |
1,700万円 |
|
|
599万円 |
700万円 |
1,440万円 |
|
|
498万円 |
600万円 |
1,220万円 |
|
|
409万円 |
500万円 |
1,030万円 |
|
|
324万円 |
400万円 |
830万円 |
|
|
255万円 |
300万円 |
670万円 |
|
|
187万円 |
200万円 |
530万円 |
|
|
135万円 |
150万円 |
400万円 |
|
|
93万円 |
100万円 |
280万円 |
|
|
57万円 |
60万円 |
180万円 |
|
|
32万円 |
40万円 |
110万円 |
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことに対する、精神的苦痛への補償を指します。
以下のように、自賠責基準の場合は「慰謝料を請求する遺族は何人いるのか」により金額を算定し、任意保険基準・弁護士基準の場合は「被害者はどのような立場だったか」などによって金額を算定しています。
<自賠責基準の相場表>
|
請求する要項 |
慰謝料額 |
|
死者本人に対する慰謝料 |
350万円 |
|
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が被害者によって扶養されていたケースのみ200万円が加算
(遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)
<任意保険基準・弁護士基準の相場表>
|
死亡者の立場 |
任意保険基準(目安) |
弁護士基準 |
|
一家の支柱 |
1,500~2,000万円 |
2,800万円 |
|
配偶者、母親 |
1500~2000万円 |
2500万円 |
|
上記以外 |
1200~1500万円 |
2000万~2500万円 |
※被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合わせた額
ここでは、軽傷を負った場合・後遺障害が残った場合・被害者が死亡した場合の3ケースに分けて、それぞれの示談金の請求例を紹介します。また、ここで紹介するものは大まかな計算例であるため、あくまで参考の一つとしていただければと思います。
なお示談金の請求にあたって、被害者については以下のようなケースを想定します。
|
「事故により打撲を負い、1ヶ月(通院日数10日)通院して7日間仕事を休んだ」というような場合、示談金の請求例としては以下の通りです。
|
自賠責基準 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
|
|
入院費・通院費 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
|
休業損害 |
7万円 |
7万円 |
7万円 |
|
入通院慰謝料 |
8万4,000円 |
12万6,000円 |
28万円 |
|
合計 |
20万4,000円 |
24万6,000円 |
40万円 |
「事故により負った骨折が後遺障害等級9級に認定され、6ヶ月(通院日数60日)通院して1ヶ月仕事を休んだ」というような場合、示談金の請求例としては以下の通りです。
|
自賠責基準 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
|
|
入院費・通院費 |
50万円 |
50万円 |
50万円 |
|
休業損害 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
|
後遺障害逸失利益 |
約1,845万円 |
約1,845万円 |
約1,845万円 |
|
入通院慰謝料 |
50万4,000円 |
64万2,000円 |
116万円 |
|
後遺障害慰謝料 |
255万円 |
300万円 |
670万円 |
|
合計 |
2,230万4,000円 |
2,289万2,000円 |
2,711万円 |
「事故により、一家の主である被害者が亡くなった」というような場合、示談金の請求例としては以下の通りです。
|
自賠責基準 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
|
|
葬儀代 |
60万円 |
※100万円 |
130万円 |
|
死亡逸失利益 |
約3,942万円 |
約3,942万円 |
約3,942万円 |
|
死亡慰謝料 |
1,200万円 |
2,000万円 |
2,800万円 |
|
合計 |
5,202万円 |
6,042万円 |
6,872万円 |
※任意保険基準については、保険会社によって設けられている基準がそれぞれ異なることから、おおよその金額を記載しています。
相手方の保険会社と協議・交渉を進めるに当たり、自身で交渉してもうまくいかないことも十分考えられます。
相手保険会社は交通事故処理を日常的に取り扱っており、損害計算等について一定の知識・経験があります。他方、被害者は「交通事故に遭ったのは初めて」という場合が大半であり、どうしても知識・経験に差があり、思うように交渉を進められないことが多いです。
そのため、保険会社と本気で協議・交渉をしたいのであれば、こちらも専門的知識を有する弁護士に依頼して、相手以上の交渉力を身につけるべきでしょう。しかし、全てのケースで弁護士に依頼できるとは限りませんので、最低限の対応として、示談にあたっては「増額のためのポイント」を押さえておくことをおすすめします。
「交通事故の示談金の内訳」でも取り上げたように、慰謝料の金額は弁護士基準で算定した場合が最も高額となる傾向にあります。そのため、相手保険会社と交渉する際も、弁護士基準での慰謝料計算を主張することで、相対的に高額の慰謝料を獲得できるかもしれません。
なお上記のとおり、保険会社は弁護士の介入がない場合には、弁護士基準で算定することを渋る傾向にあるようです。そのため、保険会社との交渉で「弁護士基準で計算して欲しい」と希望しても、やんわりと拒否される可能性は否定できません。もし、相手とうまく交渉が進められないようであれば、速やかに弁護士に依頼した方が良いかもしれません。
後遺障害の補償は、それ自体が負傷に対する補償額を大きく上回る傾向にあります。もっとも、実際に後遺障害について補償を受けるのであれば、まずは相手の自賠責保険会社から後遺障害認定を受けるべきです。後遺障害補償は、当該認定された等級に基づいて行われるのが一般的です。
この点、後遺障害に係る補償額は認定される等級が1つ上がるだけでも大きく増額します。例えば、「交通事故の示談金の内訳」で紹介した相場表を見てもわかるように、弁護士基準において、もし後遺障害第8級から第7級に上がった場合は200万円もの増額が見込まれます。
したがって、被害者側からすれば後遺障害認定の申請手続きを行う場合は、できる限り高い等級認定を目指して手続きを勧めるべきといえるでしょう。この場合、例えば、申請時で必要となる「後遺障害診断書」について必要十分な記載がされているかとか、後遺障害があることを基礎づける資料としてどのようなものを添付するべきかといった点について慎重な検討は必要です。
当該検討は、率直に言って交通事故についての知識・経験のない素人には無理があります。そのため、少しでも高い(適正な)後遺障害等級の認定を受けたいということであれば、早めに弁護士に依頼する方が適切かもしれません。
関連記事:後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント
「交通事故の示談金が増額するポイント」で解説した通り、示談を行う際は弁護士のサポートを得ることで示談金の増額が望めます。また交通事故の場合、「被害者の症状」や「後遺障害の程度」だけでなく「過失割合」なども絡んできますので、スムーズに問題を解決するためにも弁護士に依頼するべきでしょう。
なお依頼時は交通事故を得意としている弁護士を選ぶことで、依頼者にとって少しでも有利に働くよう、手厚いサポートが望めるでしょう。しかしなかには、「どうやって探せばいいのかわからない」という方も多いかと思います。
弁護士選びに慣れていないという方には、当サイト『あなたの弁護士』がおすすめです。
『あなたの弁護士』では「交通事故問題を得意とする弁護士を探したい」「都内で探したい」「気軽に無料相談できる所が良い」など、希望内容に応じた弁護士検索が可能です。まずは一度利用してみましょう。
交通事故における示談金の内訳や、金額を決める基準などについてお分かりいただけましたでしょうか。
示談にあたっては、特に「相手方から提示された示談金が適切な額かどうか」を判断するための知識を持っておくことが大事になります。
もし対応に不安を感じていたり、何かお困りの点があったりする場合は、ぜひ『あなたの弁護士』から希望条件に合った弁護士に頼ることをおすすめします。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


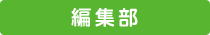
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。