決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


送り付け商法(おくりつけしょうほう)とは、注文を受けていないにも関わらず事業者が消費者に商品を送り付けて金銭を請求する商法のことで、『ネガティブ・オプション』『押し付け販売』『カニカニ詐欺』などともいいます。
件数は減っているものの、2016年には1,816件の相談が国民生活センターに寄せられています。
今回は、送り付け商法の手口と事例、被害に遭わないための対策と、遭ってしまった後の対処法などをお伝えします。
目次
電話などで強引にカニなどの商品を勧め、根負けした消費者が買うと言ったら高額な商品を送り付けることが典型的な手口です。
しかし、それ以外にも葬儀の後の忙しいときにどさくさに紛れて商品を送り付けたり、無料と思わせて契約をした消費者に有料の商品を送り付けたりする手口もあります。詳しく確認していきましょう。
送り付け商法では、代引きの仕組みを利用してお金を騙し取ることがよくあります。本物の配達員がやってくるので、お金を払わなければいけないような気になってしまいます。
カニや健康食品などが自宅に届きます。受け取ってしまった方は、購入していないのにいきなり高額な商品を送り付けられ焦ってしまうかもしれません。
特にカニは生ものですから、「返品やクーリング・オフはできないだろう…。」と考えてしまうかもしれません。
故人が頼んだものと思わせる手口です。遺族は故人が頼んだかどうか確認のしようがありませんし、ただでさえ忙しい葬儀の後ですから、うっかり支払ってしまうことも考えられます。
電話やアンケートなどで無料プレゼントのように思わせ、商品の送付に合意した消費者に有料の商品を送りつける手口です。
街頭などでアンケートをやっている振りをし、チェック項目の中にさり気なく商品購入の項目を紛れ込ませておく手口です。
怒鳴り声をあげて強引に消費者の反論を押さえ込み商品を送る場合もありますが、実際は声が大きいだけで内容はめちゃくちゃです。
カニはクーリング・オフできますし、食べたいと言っただけでは契約は成立しません。したがって取り立てもできません。
声の大きさと発言内容の正しさはイコールではないので、騙されないようにしましょう。
送り付け商法は代引き料金さえ払わなければ被害に遭いようがないのですが、会社に送られてきたときなどは『誰かが頼んだのかな』とうっかり立て替えてしまうこともあります。
返品の電話をしてトラブルになることを避けて、自分が我慢すれば済むかなとしぶしぶお金を出してしまう人もいるかもしれません。
しかし、安易に泣き寝入りをしてしまうと、何度も商品か送られてきます。消費者はみんながみんな騙されやすいわけではないので、騙されやすい人は貴重なわけです。
一度騙されると詐欺師が管理しているカモリストに名前や電話番号、住所が載るため、手を変え品を変えた詐欺や悪徳商法のターゲットになり得ます。
ここでは、国民生活センターに寄せられた相談事例を確認していきましょう。
魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように『今の時期何が食べたいか』と聞かれた。思わず『カニかねえ』と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、『今カニを送ったよ。もう返せないよ』と言われた。驚いて『なぜ送るのか』と反論したが『今食べたいと言ったじゃないか』と怒鳴られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが『教える必要はない。品物が届けばわかる』と教えてもらえず、らちが明かないと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり『一方的に切ったな。カニは送る』と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女性)
買うと言っていないので、カニが送られてきてもお金を払う必要はありません。
ただ、この事例の場合の被害者は高齢者です。判断能力が衰えている場合もあるので、なかなか断れないかもしれません。高齢者は詐欺のターゲットになりやすいですから、ご家族の助けが必要です。
1回だけカニを購入した業者から『今なら2万5,000円を2万円にする』と電話があった。値引きするならと了承したが、よく考えると高額に思えて、翌日キャンセルの電話をした。業者から、『こういうものはクーリング・オフできない。キャンセルは認めない。商品を送付してやる』と怒鳴られた。(70歳代 男性)
引用元:国民生活センター
被害者は業者に『クーリングオフできない』と言われていますが、これはクーリングオフ妨害行為にあたるので、商品を受け取って8日を過ぎていてもクーリングオフが可能です。
また、被害者は一度業者からカニを購入しているので、もしかすると前回も高額なお金を支払った可能性があります。一度騙されるとカモにされやすいので注意が必要です。
送り付け商法に遭った際の手口と対策を知っておけば、お金を騙し取られそうになっても騙されていると気づきやすくなります。ここでは、送り付け商法の被害に遭わないための対策を見ていきましょう。
相手がしつこかろうが、怒鳴っていようがいらないものはいらないと断ってください。相手のしつこさが鬱陶しくなってこちらが折れても、カモリストに載せられ再びターゲットにされるのがオチです。
断らないともっと面倒なことになると覚えておきましょう。
頼んでいないものが代引きで届いたからといってお金を払う必要はありません。電話番号を変えられたり、架空の住所が使われていたりすることもあり、一度お金を払ってしまうと取り戻せる保証はありません。
支払わなければ被害に遭いようがありませんから、自分が契約したもの以外にはお金を出さないようにしましょう。
あなたが大丈夫でもご家族に高齢の方がいらっしゃるなら、そのご家族の心配もした方がいいかもしれません。以下の対策をしておくと、送り付け商法以外の悪徳商法や詐欺に対しても有効です。
送り付け商法にあった際の対策は主に以下の4つです。
詳しく確認していきましょう。
頼んでいない商品が代引きで送られてきたときにお金を払わないでよい理由は、そもそも契約が成立していないからです。
契約が成立するには、『申し込み』と『承諾』の2つがなければいけません。送り付け商法の場合は、業者が商品を買ってくださいという『申し込み』をしているので、あなたが買いますと『承諾』しないことには契約が成立しません。
ただし、届いたカニを食べてしまったときなどは承諾とみなされる可能性があるので、商品は使用せず保管しておきましょう。
送られてきた商品を受け取らないというのも手です。そもそも相手が勝手に送ってきたものですから契約が成立していませんので、受け取る義務もありません。
受け取ってしまうと、クーリングオフをするために荷物を保管する義務が生じてしまいますから対応の仕方が変わってきます。
商品を受け取ってしまった場合、使用していなければ商品の所有権は業者側にあります。
クーリングオフで返品する場合、業者はあなたに商品返還を請求する権利を得ます。請求の期限は14日ですから、その間は使わないで保管しておきましょう。
業者に商品引取りの申し出をすると保管の期限が7日間に短縮されます。
保管期限が過ぎると業者は商品返還を請求する権利を失いますから、残った商品はあなたの好きなようにして構いません。
商品を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。契約書を受け取っていなかったり、クーリングオフ妨害が遭った場合は8日以降でもクーリングオフできます。
ハガキに次のように記入して両面のコピーをとり、特定記録郵便や簡易書留など証拠が残る方法で販売会社に送りましょう。
送り付け商法をする業者は断られたりクーリングオフすると言われたときの対処法をよく知っている可能性があります。ですから、スムーズにクーリングオフできないときもあるでしょう。
そんなときは次の相談先に連絡すると、具体的にどう対処すればよいのかを教えてくれます。
最後に、送り付け商法にあった際の相談先を確認しましょう。
110番は緊急の事件のときの連絡先であるのに対し、#9110は生活の安全に関する相談ができる窓口です。専門の相談員に相談に乗ってもらえます。
参照元:警察#9110
消費者被害から消費者を守るために設置された独立行政法人です。スムーズにクーリングオフをさせてもらえないときなど、困ったときに具体的な対処法を教えてくれます。
参照元:国民生活センター
被害額が高額な場合は弁護士に依頼することで、お金を取り戻すために動いてもらえます。依頼する際は消費者被害に詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。
送り付け商法では、いきなり家に商品が送られてきますし、電話をしても業者がまともに取り合ってくれないのでどう対応してよいのかわからず、途方に暮れるかと思います。
ただ、『申込み』と『承諾』がないために契約は成立していませんので、あなたはお金を払う義務はありません。
覚えのない商品が届いても、お金を払ったり商品を受け取ったりしないようにしましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


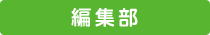
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。