決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


交通事故における示談交渉は、加害者の任意保険会社と被害者の両者で話し合って示談金額を決めることであり、示談金が被害者へ支払われることで問題が解消されるようになります。
しかし、任意保険会社との交渉では被害者が不利な条件で示談が成立されてしまう可能性もあり、ケガや後遺障害の精神的負担に見合った示談金を受け取れないことが考えられます。被害者と任意保険会社の間で、平等な立場で話し合いが進むとは限りません。保険金の支払いをなるべく抑えたいと思っている任意保険会社に対し、被害者は正当な主張を続けることが重要となります。
そこで今回は、交通事故における示談交渉の手順を確認していき、保険会社との示談交渉を有利に進めるためのポイントを解説していきます。示談交渉を行うタイミングも大事になりますので、任意保険会社側のペースで交渉を進めないように心掛けましょう。
他にも、交通事故で適正な示談金を受け取るために必要な知識は多数あります。
一度下記より、不足している知識についてもご確認頂くことをお勧めします。
|
交通事故の示談に関する知識一覧 |
目次
示談とは、交通事故を起こした加害者と被害者との話し合いによる解決であり、最終的に加害者から被害者へどれほどの示談金を支払えば両者が納得するのかを交渉することになります。
裁判で争われる前の段階で、当事者同士で自主的な和解をするための話し合いが示談交渉です。一般的には示談書を取り交わし、被害状況や示談金額、支払方法(支払期日、分割払いの指定)を書面で確認した被害者は署名をして任意保険会社へ提出し、示談成立を済ませます。
加害者側の任意保険会社より支払われる示談金の内訳は、財産的損害と精神的損害の2種類になります。慰謝料は被害者の精神的苦痛に対する補償であり、対して財産的損害は実際に被害者が支出を余儀なくされた医療費や入院費などの補償です。
一般的に、示談金と慰謝料は同じ意味だと考えられているかもしれませんが、厳密には上記のような内訳になりますので、正確には慰謝料は示談金の一部だといえます。
通常、交通事故の示談交渉では加害者本人と直接話すことはなく、加害者側の任意保険会社と被害者が話し合うことになります。というのも、自動車の所有者(運転者)の多くは強制加入である自賠責保険に合わせて任意で自動車保険に加入しているからです。
また、被害者側も任意保険(自動車保険)に入っている場合は、それぞれの任意保険会社の担当者同士で示談交渉を進めるケースも考えられます。ただし、被害者側の保険会社であっても完全に信用できる訳ではなく、被害者の主張を無視して保険会社同士で勝手に示談を成立させる可能性もありますので注意するべきでしょう。
続いて、交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れを見ていきましょう。事故後の被害者は治療に専念することも大事ですが、治療を続けてもケガが回復せず、後遺障害として残ってしまうこともあります。その場合は後遺障害等級認定の申請をして、後遺障害に関する慰謝料を示談金として請求するようにしましょう。
図:交通事故発生からの流れ
交通事故後の対応では、すぐに被害者の身元を確認することが重要です。加害者側が事故現場から逃げてしまう可能性もあるため、名前や連絡を聞いて控えるようにしましょう。また、加害者が勤務中で営業車等での移動という状況であったら、名刺をもらって相手の身元を確認した方が良いですね。
また、事故発生の直後では痛みがなく受傷していないと思っても、後々になって事故による症状が発生することもあります。その場合は警察への届出が『物損事故』扱いになっている可能性があるため、医師からの診断書を警察に提出して『人身事故』に変更してもらうようにしましょう。物損事故のままだと保険会社に治療費の支給が認めてもらえない場合があるので、よく確認するべきポイントとなります。
交通事故によるケガの治療において、病院から健康保険の利用を拒否されるケースもありますが、保険適用外の自由診療で治療を行えば被害者側の負担が大きくなりますので、健康保険や労災保険を利用した方が良いでしょう。
交通事故で健康保険が絶対に使えないということはなく、『第三者行為による傷病届』という書類を社会保険事務所に提出すれば健康保険の利用が可能になりますので覚えておくようにしましょう。
治療を続けても症状が一向に良くならない場合、『症状固定』だと判断されます。症状固定について医師から通告されると後遺障害等級の認定申請が可能になりますが、治療を継続しても回復しない状態なので治療費の請求ができなくなります。
また、加害者側の任意保険会社より強制的に症状固定を決めさせられて治療費の打ち切りを促される場合がありますが、素直に応じず担当の医師とよく相談するようにしましょう。
参照元:「症状固定で損をしない方法」
症状固定後は後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害を負ったことで普段の生活や労務上で支障が生じることを証明し、後遺障害慰謝料のほか労働能力の喪失により将来的な収入の減少を意味する後遺障害逸失利益に対する損害賠償を請求する必要があります。
後遺障害等級の認定申請では2種類の申請方法がありますが、より確実に等級認定してもらうためには『被害者請求』での申請手続きがオススメです。
参照元:「被害者請求のメリット」
後遺障害等級の認定を受けてから保険会社との示談交渉が始まります。被害者は自分が請求するべき慰謝料や損害賠償金の相場や算出方法を確認し、保険会社から提示された示談金が妥当な額であるかどうかを見極めるようにしましょう。
示談金の一部である慰謝料については相場を決める基準が複数あり、一般的に加害者の任意保険会社より提示される慰謝料額は、低い相場額である『自賠責基準』で決められたものです。決して被害者の精神的苦痛に見合う額とはいえない場合がありますので、弁護士に相談して示談金を再交渉してもらった方が良いケースも考えられます。
なお、交通事故によってもらえる慰謝料額や相場基準については「交通事故慰謝料の計算方法」で詳しく解説していますのでご参考ください。
被害者が示談書に署名をした時点で示談は成立します。基本的には示談を撤回することは難しいので、示談金に関する契約内容をよく確認した上で同意するようにしましょう。
上記における交通事故から示談成立までの流れを見ていただくとお分かりいただけますが、被害者が後遺障害を負った場合、基本的には等級認定後のタイミングで示談交渉を行うものとされています。
注意するべき点として、まだ治療が完全に終わっていない段階で加害者側の任意保険会社より示談の要望があった場合です。早期示談は治療費の打ち切りや被害者の刑事罰を軽くすることなどの目的があり、任意保険会社側の都合による催促が考えられます。
また、症状固定前での示談だと医療費が確定していない状態なので損賠賠償金が減らされる可能性もあるため、被害者が損をしてしまうこともあり得ます。
参照元:「症状固定前の示談は要注意」
基本的にはケガが完治した段階で示談交渉を始めるようにしましょう。実際に被害者が支払った治療費のほか、治療期間を基に決められる入通院慰謝料もハッキリさせてから交渉をした方が望ましいです。
また、症状の程度が重い後遺障害であった場合は、該当等級によって慰謝料額の基準が異なりますので、後遺障害等級の認定を受けてから任意保険会社との示談交渉をする流れになります。
示談交渉をする時期は治療を済ませた後が良いと説明しましたが、治療が長引く場合は時効について気にする必要があります。
ひき逃げされて加害者が不明な場合を除き、交通事故による損害賠償の請求権は事故日より3年以内であると法律上で定められています。
※ひき逃げにより加害者が分からない場合の時効は20年です。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 第724条
長期間の治療以外にも、加害者が被害者との示談交渉に応じず先延ばしにされてしまう場合も3年の請求可能期間を超えてしまう恐れがあります。
細かな話になりますが、時効の起算日については後遺障害であるかどうかで定義が異なります。
後遺障害に対する慰謝料については、事故日ではなく治療しても回復しなくなった症状固定日の翌日が起算日になります。
後遺障害に該当しないケガに対する損賠賠償に関しては、事故発生日が時効の起算日になります。
被害者と遺族が請求できる死亡慰謝料については、被害者の死亡日の翌日から3年(または20年)以内が請求期間になります。
時効の起算日より3年が経過すれば、加害者側へ損害賠償を請求する権利を失うことになりますので、示談交渉が長くなりそうであれば時効を中断させるべきでしょう。
時効を中断させる方法は以下の方法がありますが、正確には時効の中断ではなく時効期間の計上をやり直すことになります。下記の方法を取れば損害賠償の請求可能な期間がリセットされて、新たな起算日から3年の時効が開始されます。
書類を提出して保険会社へ時効の中断を承認してもらうことも可能です。
示談交渉の流れや適切な時期について説明しましたが、保険会社と実際に示談を取り交わす上では安易に同意しないようにしましょう。
一度応じた示談については覆せないため、口約束であっても即答は避けた方が良いでしょう。特に治療を終える前の早期的な示談を持ち掛けられても応じず、後遺障害に該当する場合は症状固定するまで待った方が適切です。
被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行うことでのメリットは等級認定が受けやすくなることに加え、保険金の支払い時期にも関わっています。
後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉を始めることになりますが、被害者請求は等級認定時に自賠責保険金を受け取れるのに対し、事前認定は示談成立後でなければ保険金を受け取ることができません。
事前認定の場合であると任意保険会社より不利な条件を提示される可能性が高くなり、「この支払条件で応じないと示談金は渡せない」と言われる場合もあるため、被害者は少ない賠償金でも示談に応じなければならない状況になってしまいます。
このように、示談交渉における任意保険会社と被害者の立場が等級認定申請の方法によって変わることを考慮すると、事前認定でなく被害者請求を利用した方が良いと思われます。
保険会社から不利益な示談内容を提示された場合、被害者自身での交渉が難しいようであれば専門家である弁護士へ依頼することをオススメします。交通事故関連に詳しい弁護士であれば事故状況や被害者の症状に応じた妥当な額の示談金を判断して、保険会社と上手く交渉してくれることが期待できます。
被害者が加入している任意保険(自動車保険)に『弁護士特約』のオプションが付いていれば、弁護士への依頼費用が最大で300万円まで補償されますのでとても便利です。
被害者の過失割合が0の場合でしか弁護士特約が使用できないと認識している方もいるようですが、実際には被害者側の過失が発生しても弁護士特約の補償が効く契約になっている場合が多いです。弁護士特約の対象可否については保険会社だけでなく弁護士側にも相談すれば分かる場合もあるので、依頼費用を含めて専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
交通事故における示談交渉について解説しましたが、加害者側の任意保険会社と比較して被害者側の立場は弱いため、十分な額の示談金を請求するためには後遺障害等級認定の申請方法や示談交渉のタイミングなどで気を付ける必要があります。
任意保険会社の示談内容に不満があったり、被害者本人での交渉に不安を感じる場合は弁護士の力を借りるのも一つの手段です。交通事故のショックや後遺障害による精神的なダメージを深く負った状態であればなおさら、被害者一人で抱え込まず専門家に頼る方が良いでしょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


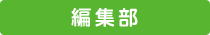
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。