決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


被相続人が生前に、相続人を受取人とする生命保険契約を締結することは珍しくありません。
近年は相続税の節税という観点からも生命保険契約が注目を集めていますが、相続における生命保険金の扱いは他の相続財産とやや異なるものとなっているため、利用の前には充分な検討が必要と言えるでしょう。
原則として、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象財産には含まれず、遺留分減殺請求の対象にもなりません。しかし、一定の場合には他の財産と同じように遺産分割で考慮されたり、遺留分減殺請求の対象とされることがあります。
また、遺産分割等の対象にならない=必ずしも非課税というわけではありませんので、税金に関しては別ということを覚えておかなければなりません。
今回は、生命保険金が相続の際にどのように扱われるか、遺産分割や遺留分減殺請求、相続税などの観点からご紹介していきたいと思います。
|
遺留分減殺請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
生命保険金は、生命保険契約によって被保険者等が死亡後に指定された受取人に支払われる金銭で、死亡保険金とも呼ばれています。
死亡保険金は、相続の場面でしばしば争いの種になるものですが、民法と相続税法とで扱いが異なってくるため、両者を区別してきちんと理解することが大切です。
まずは、生命保険金の相続での扱いについて、基本的な知識をご紹介いたします。
生命保険金は、保険契約に基づいて被保険者の死亡等の事由により受取人に支払われるものであり、相続財産とならないのが原則です。
しかし、相続と同じように人の死亡を原因として一定の金銭が支払われ、受け取る額も比較的高額になることから、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われ、民法上も一定の場合に特別受益として考慮されるなど、相続と無関係とは言えません。
したがって、生命保険金の性質としては以下の3点をきちんと理解することが大切です。
生命保険金は相続財産ではないため、原則として遺産分割の対象財産にはならず、受取人に指定された人が固有の権利として生命保険金請求権を取得するとされています(最判平成14年11月5日)。
しかし、支払われる生命保険金は比較的高額になる場合が多く、これを一切考慮しないで遺産分割等がなされると、相続人間の公平を欠くおそれがあることから、
| 保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、……特別受益に準じて持戻しの対象となる(最決平成16年10月29日) |
とされています。
なお、生命保険金について、受取人を単に「相続人」と指定した場合であっても相続財産に含まれることはありませんが、約款によって複数の相続人が生命保険金請求権を取得する場合は、法定相続分に関わらず均等割での請求権を取得するとされています(最判平成5年9月7日)。
生命保険金が相続財産に含まれない以上、原則として遺留分減殺請求の対象財産にもなりませんから、取得した生命保険金に対して遺留分減殺請求を行うことはできないと考えるのが通常です。
しかし、生命保険金の払込保険料に関しては、特別受益として考えることができるため、この部分は遺留分算定の際に考慮しても良いでしょう。(※詳しくは後述)
生命保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」に含まれ(相続税法3条1号)、相続税の課税対象財産になります。ただし、保険料の負担者によっては、相続税でなく所得税や贈与税が課税されることになりますので、どういった契約に基づいて支払われたかを確認する必要があります。
| 被保険者 | 保険料の負担者 | 受取人 | 課税される税金 |
| 被相続人 | 被相続人 | 相続人等 | 相続税 |
| 相続人A | 相続人A | 所得税 | |
| 相続人A | 相続人B(保険料負担者以外の人) | 贈与税 |
生命保険金に相続税が課税される場合、法定相続人の数×500万円を非課税限度額とされ、全ての相続人が取得した保険金の合計額からこれを差し引いた部分だけが相続税の課税対象になります。
ただし、この場合でも相続人以外の人(孫や相続人でない親族など)が生命保険金を取得すると非課税の適用はありません。
なお、生命保険金にかかる相続税については、次の計算式を利用して算出することができます。
相続人に課税される生命保険金の金額=その相続人が受け取った生命保険金額―非課税限度額×その相続人が受け取った生命保険金額÷全相続人が受け取った生命保険金の合計額
例えば配偶者が1,000万円、子3人がそれぞれ800万円ずつ生命保険金を受け取ったとします。
このとき、子それぞれに課税される生命保険金の額としては、
が課税対象となります。
とはいえ、相続税には基礎控除や各種控除制度がありますので、課税対象となっていても実際の納付額が0円で済む可能性がありますから、申告の要否を含め余裕を持って相続税の計算を行うことをおすすめします。
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。
このことから、原則として遺留分減殺請求の対象財産にはなりません。
とはいえ、遺留分制度の趣旨は遺族の生活保障の意味合いも持ちますので、相続財産がほとんどなく生命保険金が唯一の財産と言えるような場合に、生命保険金に対して何らの請求もできないというのは相続人間の公平を著しく欠くことになりますから、例外的に遺留分減殺ができる可能性があります。
ここでは、遺留分減殺請求と生命保険金の関係について、少し踏み込んでご紹介していきたいと思います。
生命保険金が遺留分減殺請求対象になる可能性があるのは、以下の3点を満たすようなケースです(なお、実務では遺留分減殺の対象とするより、むしろ生命保険金に対する法定相続分を主張する方が通常ではないかと思われます。)。
生命保険金が遺産分割や遺留分減殺請求で考慮される場合は、それが「特別受益」に準じるものと認められる必要がありますから、相続人でない第三者が保険金を受け取っている場合には、特別受益の問題を生じません。
ということは、愛人や内縁の配偶者を受取人として生命保険契約をしてしまえば、これらの人に財産を残せるようにも思えますが、実務上、愛人等を受取人とする生命保険契約を締結することは非常に厳しい条件が課せられており、現実的にはほとんど不可能となっているため、あまり心配しなくて良いかと思います。
なお、これらの人の子(非嫡出子)を受取人とする場合は充分考えられますが、非嫡出子は認知されれば相続人になりますので、①の条件を満たすと言えます。
例えば相続財産が3,000万円しかないのに、生命保険金が3億円あったような場合は、保険金が著しく高額であるため「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない」
著しい不公平が生じていると判断される可能性が高いのに対し、相続財産が3,000万円で、生命保険金が300万円だったような場合では、著しい不公平が生じていると言えないかと思います。
このように、相続財産と保険金の額を比べて保険金が著しく高額である場合には、生命保険金も遺産分割や遺留分減殺請求の対象になると判断される可能性が高いでしょう。
また、下級審の裁判例では、およそ1億円の相続財産に対し、特定の相続人が約1億円の保険金を受け取った事案について、「遺産総額に匹敵する巨額の利益を得ている」として特段の事情が存在すると判断したものもあります(東京高判平成17年10月27日)。
その他の裁判例としては、遺産の約61%に匹敵する額の生命保険金を受け取った事案で特段の事情を認定したものもあり、相続人の人数や遺産の内容によって判断が分かれる傾向にあります。
実際には、当該金額の比較に加えて、下記の③も踏まえて総合判断されているのが実情であり、上記3000万円と3億円の事例のように明らかに不公平という場合でなければ、判断はケース・バイ・ケースとなるでしょう。
②に関連しますが、著しく不公平と言えるかどうかは、受け取った保険金の金額のほか、被相続人と受取人・相続人それぞれの関係性によっても判断が分かれます。
例えば被相続人と同居し献身的に介護していた相続人が高額な生命保険金を受け取った場合、同居せず介護費用も負担していない他の相続人と差がつくのは当然の区別と言うことができますし、逆にこういった事情が一切なく特定の相続人が不自然に巨額の保険金を受け取るのは著しく不公平と言える可能性があります。
また、生前贈与等で充分な財産を取得していた相続人を除いて他の相続人に生命保険金を受け取らせるケースもあるなど、著しく不公平と言えるか否かは被相続人の生前の生活状況にも大きく左右されることになります。
このように、「民法903条(特別受益)の趣旨から到底是認できないほどの著しい不公平があるか否か」については、事案に即した具体的な判断が行われることになり、確立した判例はありません。
しかがって、他の相続人が受け取った生命保険金について争いたい場合には、弁護士等の相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
その際、生命保険金は高額になるのが一般的なので、代理権限に制限のある司法書士でなく、制限のない弁護士へ相談したほうが手間は少ないかと思いますので、併せてご検討いただければ幸いです。
生命保険金と遺留分についての参考判例としては、最決平成16年10月29日が挙げられます。この判例は、簡単に言えば「生命保険金が特別受益に準じて考慮される可能性がある」ということを明示したものになっています。
この事案は、被相続人の子4人のうち、長男を相手取り長女・四男・次女の3人(※残りの子は既に死亡しており、代襲相続なし)が遺産分割審判を申し立て、長男の取得した生命保険金が分割対象となるか否かが争われたものです。
このとき、被相続人の相続財産はほぼ不動産のみで、一部財産についての遺産分割の結果、長男および3人の相続人は約1,200万円~1,400万円相当の財産をそれぞれ取得しています。
長男は自宅を増築して被相続人と同居し介護などにも関わっていましたが、その他の相続人はこのようなことをしていなかったという事情がありました。
本件では、残った相続財産であるA土地についての遺産分割と、その際に長男の取得した生命保険金が考慮されるか否かが争われており、A土地を長男が自宅および鉄工業の事業場として利用していることから、どういった分割をしていくかが問題になりました。
最高裁は、大きく次のように判断しています。
生命保険金(死亡保険金)請求権は、保険金受取人が原始取得した固有の権利であり、被相続人から承継取得するものではなく相続財産に属することもない(最判昭和40年2月2日)。
死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないため、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない (最判平成14年11月5日)。
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当であるが、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどを考慮すると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
以上のことを考慮したうえで、最高裁は
という判断をしており、判決としては抗告棄却になっています。
この事案では生命保険金が特別受益に準じるものに該当しないと判断されていますが、事案によっては特別受益に準じて考慮される可能性があるということを明示していますので、非常に重要な判例と言うことができるでしょう。
冒頭から何度も述べているように、生命保険金はいわゆる相続財産には含まれないのが原則ですが、相続税法上は相続税の課税対象財産に含まれることになり、民法と相続税法とで扱いが異なる財産と言うことができます。
また、相続人間の不公平が到底是認できないほど著しいような特段の事情がある場合には、例外的に相続財産に準じて考慮される場合がありますので、こういったケースでは相続に詳しい弁護士等へ迷わず相談することをおすすめします。
遺留分減殺請求は、具体的な事案によって請求できるかどうかの判断や金額が異なってきますので、依頼するかは別として、弁護士の意見を聞いてから請求をしたほうが良いかと思います。
多くの事務所で無料相談の受付を行っていますし、法テラスなどを経由して相談することもできますから、電話・メール・面談などあなたに合った手段を活用して弁護士の意見を聞いてみてくださいね。
|
遺留分減殺請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


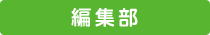
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。