決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


遺留分減殺請求をするとき、不動産のなかでも評価額がつけにくいといわれているのが土地であることはご存知ですか?購入したときより価格が下がるものですが、中には上がる不動産も時々あります。
そうした土地をはじめとした不動産が遺留分の対象だったとき、トラブルに発展することが多く穏便に済むほうが少ないとも言われているくらいです。
この記事ではそんな遺留分について、主に土地に関する内容をご紹介していきます。
|
遺留分について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
被相続人の財産は、被相続人の意思により自由に処分できるのが原則です。
しかし、この原則も絶対的なものではなく、被相続人によっても侵害することができない法定相続人のために保障される相続分というものがあります。これが遺留分です。
そのため、被相続人の意思であっても、法定相続人の遺留分を侵害するような財産処分が行われた場合、これを侵害された法定相続人は、侵害された権利について補償を求めることができます。これが遺留分侵害額請求です(2019年7月1日の法改正以前の相続の場合は遺留分減殺請求)。
法定相続人の遺留分の計算方法は以下の通りです。
遺留分=遺留分の基礎となる財産×遺留分割合
遺留分の基礎となる財産の算出方法は以下の通りです。
遺留分の基礎となる財産=相続開始時に有した財産の価額+生前贈与・遺贈等により移転した財産のうち持戻対象となる財産の価額-相続開始時に被相続人が負担する債務額
1.遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2.条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)引用元:民法第1029条
相続開始時に被相続人が保有する財産の評価額です。
不動産など金額が明確でないものについてはその評価額を計上することになります。
遺留分算定に計上される移転財産は、一般的には以下のような財産とされています。
法定相続人の遺留分割合は法律上以下のとおりです。
|
法定相続人の遺留分割合 |
|
|
直系尊属の場合 |
1/3 |
|
配偶者・直系卑属の場合 |
1/2 |
|
兄弟姉妹(その代襲相続者)の場合 |
0 |
上記のとおり、遺留分の計算では、被相続人の財産総額を確定させる必要があります。
そのため、被相続人の相続財産に不動産や有価証券など一義的に金額が決まらない物がある場合、その財産評価をどうするかが問題となります。
この評価額を巡り、遺留分権利者・遺留分義務者間で紛争となることは珍しいことではありません。
不動産のなかで評価額の算定が難しいといわれている土地を遺留分として計算するとき、価格は時価で計算するのが原則です。遺留分である土地を算定するときは、基本は時価で評価するものだということを念頭に入れておきましょう。
ところが、時価で評価するのは主に相続人同士で争うようなことになったときに取る手段とも言われています。実務的な面では簡便的な相続税評価額にしている、というケースもあります。
遺留分である土地の価格は時価で計算するといいましたが、その判断はいつ頃になるのでしょう。結論として、土地の評価額である時価は相続時の値段で決まります。
後日、改めて遺留分減殺請求を受けたときは、請求を受けたときではなく相続した時期の価格で計算します。これは時期により異なり、計算も微妙に違ってきますので、わからないときは弁護士などに尋ねてみましょう。
遺留分の対象財産になりやすい不動産があるとき、評価額により相続する金額も変わります。ほとんどの人ができるだけ多く受け取りたいと考えているかもしれませんが、そんなにうまくはいきません。
というのも、不動産の評価方法については複数の手段が用いられているのです。土地は時価で判断するといっても、計算方法により金額が大きく変わります。
主にどんな評価方法を採用しているのか、ご紹介しましょう。
最初に紹介するのは、「固定資産税評価額」というものです。簡単にいうと、時価よりも安く評価する手段になります。相続する側としては少なくなるのはちょっと、思うかもしれません。
評価額については、後述にてご紹介する地価公示価格という手段で算定される価格の、およそ7割といわれています。
続いて知っておきたいのが、「路線価」という評価方法です。こちらは遺留分である土地を計算するとき、時価で算定するのが原則ではあるものの、すべての土地を時価で判断するのは難しくなります。
そこで考えられたのが、道路に値段をつけ、面している土地の値段を決める手段が路線価です。路線価は毎年国税庁が設定しているので、確認してみてください。
次に知っておくと便利なのが「地価公示価格」という評価方法です。これは国土交通省の土地鑑定委員会が発表しています。
資格など関係なく誰でも参加できる公開市場などで成立した価格が、時価に近い評価額で算定されます。
最後に、こちらも土地価格を時価で判断されやすいといわれている「地価調査標準価格」というものがあります。
毎年7月1日に都道府県地価調査により調査が行われ、都道府県知事が公表する価格のことを指します。
遺留分である土地をはじめとした不動産を相続した、それですべて万々歳で終わることはありません。遺産を相続したあと、一番に考えなくてはいけないのが相続税についてです。
平成27年1月1日より相続税の基礎控除が引き下げられたのを、知っている方も多いでしょう。
具体的にどのように引き下げられたのかというと、以下の表のようになります。
| 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以降 | |
| 定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続人比例控除 | 1,000万円 ×法定相続人の数 | 600万円 ×法定相続人の数 |
相続税に対する見直しが図られたことで、これまで税金がかからなかった人も負担しなければいけないようになったのが、この改正の注目点です。例えば6,000万円の遺産があったとき、相続税は改正前と後ではどのくらい違ってくるのでしょう。法定相続人が2人の場合、以下の表のようになります。
| 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以降 | |
| 財産 | 6,000万円 | 6,000万円 |
| 定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続人比例控除 | 1,000万円×2人 | 600万円×2人 |
| 合計 | 7,000万円 | 4,200万円 |
| 相続税の額 | 0円 | 180万円 |
基礎控除が引き下げられたことと併せて、相続税率の構造も見直されるようになりました。主に1億円以上の高額遺産を相続する方が対象です。
どのように改造されたのか、そちらも表にてご紹介します。
|
平成26年12月31日以前 |
平成27年1月1日以降 |
||
|
取得金額 |
税率 |
取得金額 |
税率 |
| 1,000万円以下 | 10% | 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円以上3,000万円以下 | 15% | 1,000万円以上3,000万円以下 | 15% |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 20% | 3,000万円以上5,000万円以下 | 20% |
| 5,000万円以上1億円以下 | 30% | 5,000万円以上1億円以下 | 30% |
| 1億円以上3億円以下 | 40% | 1億円以上2億円以下 | 40% |
| 2億円以上3億円以下 | 45% | ||
| 3億円以上 | 50% | 3億円以上6億円以下 | 50% |
| 6億円以上 | 55% | ||
遺留分として土地を相続、時価で判断するのが原則といいましたが、その評価額が高くなればなるほど負担が増加します。
相続税は相続人にとって命題ともいえる事案になるので、きちんと把握しておきましょう。続いて、そんな相続税の増加額についてもっとわかりやすく、改正前と後でどのくらい増えたのか、まとめてみました。
| 相続税の課税額 | 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以降 | 増加額 |
| 7,000万円 | 0円 | 110万円 | 110万円 |
| 1億円 | 100万円 | 290万円 | 190万円 |
| 2億円 | 800万円 | 1,120万円 | 320万円 |
| 3億円 | 1,900万円 | 2,380万円 | 480万円 |
| 5億円 | 5,000万円 | 5,640万円 | 640万円 |
遺留分に関する、特に土地など不動産に関する問題は法律の専門家である弁護士への依頼が便利です。トラブルも多発するのが珍しくない案件だけに、法的なサポートがあると心強さは非常に大きいのも印象でしょう。
そのほかにもメリットとして挙げられるのが、次のような点です。
・相手との交渉をすべて代理してくれる
・調停や訴訟など、法的手段をもって解決を模索してくれる
・遺留分の請求に必要な書類を集め、作成、提出など一元的に任せられる
・いつでも気軽に相談できるので、精神的負担も軽くなる
遺留分をはじめとする相続に強い弁護士に依頼すれば、煩わしい手間を感じることなく、スムーズな解決が図れます。
では実際に依頼するとなったとき、どれくらいの負担をするのかが気になっている人がほとんどのはずです。主に必要となる着手金・報酬金ですが、弁護士により異なりますが、相場といわれる金額はある程度見ることができます。
依頼前に支払います着手金、こちらは目安となるのが30万円前後は最低でもかかります。依頼内容により前後しますが、おおよそこの程度が初期費用となるでしょう。
問題が無事解決し、弁護士にこれまでの働きとして支払う報酬金は得られた経済的利益から算定します。一般的に5%~16%の金額を、依頼が無事完了したときに支払いますが、入金が確認したときに払うのが原則です。
成功報酬なので、そこまで焦って払わないといけないお金というわけではありません。
遺留分のなかでも不動産、特に土地の評価額は時価で算定するのが一般的です。肝心の評価額は被相続人が死亡した翌日から計算する、これが原則となります。ただし、すべての土地を時価で算定することはできないので、評価方法は必ずしも1つとは限りません。
|
遺留分について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


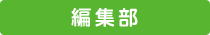
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。