決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
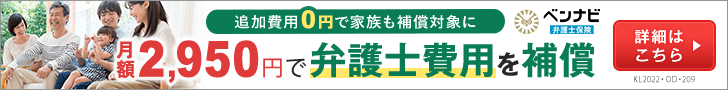
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


遺留分減殺請求とは、遺留分の権利を有する法定相続人(被相続人の配偶者・子・直系尊属※兄弟姉妹は除く)が、自己の遺留分を侵害している人に対して行うもので、大雑把に言えばこれらの人が「私にも最低限の遺産の取り分を渡しなさい」という内容の請求になっています。
遺留分の権利を有する法定相続人は、遺言等で自己の遺留分相当の財産を取得できない場合に、遺留分を侵害している相続人等に対して遺留分減殺請求を行う権利が保障されています。
そのため、例えば長男1人に全財産を相続させるというような内容の遺言があった場合に、配偶者や次男が長男に対して遺留分相当の財産を渡すよう請求するというのが遺留分減殺請求の典型例になります。
遺留分減殺請求された場合、請求者とあなたとの関係性次第では、遺留分を渡したくない(請求を拒否したい)と考えることもあるでしょうが、請求を無視し続けるというのは大きなリスクを伴うものです。
そこで今回は、遺留分減殺請求をされた場合にどういった対応をするのが良いのかをご紹介していきたいと思います。
|
遺留分減殺請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
それでは、実際に遺留分減殺請求の当事者になってしまった場合には、どういった専門家に相談するのが良いのでしょうか。
法律に詳しい専門家としては「弁護士」「司法書士」「行政書士」などが挙げられますが、このうち行政書士は、実は相続に関して扱える案件があまり広くありません。そのため、現実的なのは「弁護士」または「司法書士」への相談となり、両者がどういった案件を扱うことができるのかについて知っておくのがおすすめです。
ここでは、遺留分減殺請求に詳しい専門家について、業務内容と費用相場を交えてご紹介したいと思います。
弁護士は、法律に関するありとあらゆる相談を受けることができ、依頼人に代わって法律手続きを行うことができます。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
(引用元:弁護士法3条1項)
弁護士の代理権には制限がなく、例えばあなたが遺留分減殺請求の対応を全て任せたい場合には、あなたの代理人として相手方と交渉したり、裁判手続きなども行ってもらうことができます。
ただし、その分弁護士費用というのはやや高額になるのが一般的で、以下のような金額が費用相場となっています。
| 相談料 | 初回:5,000円~1万円/30分 一般:5,000円~2万5,000円/30分 |
| 着手金 | 最低10万円程度 ※事件の内容によって異なる |
| 報酬金 | 最低20万円程度 ※事件の内容や結果によって異なる。「成功報酬」としている場合、結果次第ではほとんどかからないこともあります。 |
| 内容証明郵便作成代行 | 1万円~5万円程度 |
費用面だけを見ると弁護士はとても高いイメージがありますが、最初から最後まで同じ事務所に一任できるというのが大きなメリットになりますので、トータルコストで考えると安上がりになるケースもあります。
(例:初めに司法書士に相談したものの、司法書士では代理できない事件に該当していた場合などには、相談自体ができなくなりますし、手続きも自分で行うしかありませんから、司法書士⇒弁護士へ相談先を変更するなどの際に余分な費用がかかるおそれがあります。※詳しくは次項にて)
司法書士は、140万円以下の法律事件についての相談および手続きの代理などを職務とする専門家で、登記に関する手続きを得意としています。
司法書士は、弁護士に比べて費用が安価というのが特徴ですが、その分扱える案件にも制限があります。
一番わかりやすい例としては、司法書士は経済的利益が140万円を超える民事事件については、相談や交渉など一切の行為ができないとされていることから、請求された遺留分が140万円を超えている場合には、司法書士への相談そのものが受け付けてもらえない可能性があるのです。
相手方の計算が間違っているなど140万円を超えているように見えて実際は超えていない場合であれば受任してもらえるケースもあるでしょうが、そうでなければ無駄足になりかねないといえますので、充分に検討した上で利用してくださいね。
| 相談料 | 無料~5,000円/30分 |
| 着手金・報酬金 | 事案や事務所によって異なる(パック料金を設定していたり、着手金無料という事務所もあります) |
| 相続登記 | 4万円前後 |
| 内容証明郵便作成代行 | 1万円~2万円程度 |
なお、いずれの専門家に依頼した場合でも、裁判等でかかる実費については別途支払う必要がありますし、日当や交通費などの費用がかかってくることになります。
一括で支払うことが難しい場合には、分割払いなどを提案してくれる事務所もありますし、費用に関する不安な点は、相談の際に遠慮なく話しておくことが大切です。
遺留分減殺請求は、特定の相続人が遺産の大半を取得した場合などに起こるのが典型例ではありますが、身に覚えのない遺留分減殺請求を受けてしまうケースも少なからずあります。
まずは、遺留分減殺請求された場合の手続きの流れと、どういったケースで遺留分減殺請求がなされるのかを整理してみましょう。
遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人(被相続人の配偶者・子・直系尊属)が、これらの人の最低限の遺産の取り分を確保するために行うものですが、請求の際には一定のルールを守らなければならないとされています。
被相続人がA、相続人が配偶者B、子C・Dという事案で具体的に考えてみましょう。
表:登場人物と相続分・遺留分の割合
|
配偶者B |
子C |
子D |
父E |
愛人F |
|
|
相続順位 |
常に相続人 |
第1順位 |
第1順位 |
第2順位 |
なし |
|
法定相続分 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
なし |
なし |
|
遺留分割合 |
1/4 |
1/8 |
1/8 |
なし |
なし |
被相続人の配偶者・子・直系尊属のうち、次の条件を満たした人だけが遺留分を請求できます。
| (1)その相続において法定相続人になっていること | この事案では、B・C・Dが相続人になることから、C・D両名が相続放棄等によって相続権を喪失しなければ、父Eは相続人になれず、遺留分権も有しません。 |
| (2)遺留分が誰かに侵害されていること | Fが遺言によって遺産のほとんどを取得した場合であっても、B・C・Dへ充分な生前贈与がなされていたなど遺留分を侵害するような相続でなかった場合には、遺留分を請求できません。 また、単に相続分が思っていたより少ないというだけで、遺留分侵害が起こっていないケースもありえます。 |
遺留分を請求できるのは、「遺留分を侵害している人」ということになります。そのため、単に自分よりも相続した財産が多いからという理由で目についた相手に適当に遺留分を請求するのは無意味で、きちんと請求の相手方を見定める必要があります。
遺留分を請求する場合、その額はあくまで「侵害された限度」の額にとどまります。そして、大抵の場合で法定相続分の半分が請求できる遺留分割合になります(※相続人の構成によって異なります)。
少しでも財産を相続していたり、生前贈与等で利益を得ていた場合には、これらの割合を元に遺留分が侵害されているかを概算するのが普通です。
遺留分は、請求した人が「あの財産が欲しい!」と言った場合でも、それが必ず認められるわけではありません。遺留分を実際に回収する際には、請求された側がどういった内容で返還するかの決定権を有します。
原則として現物返還が推奨されますが、土地や動産等の場合には代償金を支払うことで現物返還に代えることも認められていますので、請求者には選択権がないと言えます。
また、遺留分については最初に遺贈から補填(減殺)を行い、足りなければ新しい贈与から順に満足を得られるところまで遡っていくという順序が決められていますから、この点についても注意が必要です。
遺留分を請求できるのは、遺留分権利者が遺留分減殺請求できることを知ったときから「1年間」かつ「相続開始から10年以内」とされています(民法1042条)。
(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(引用元:民法1042条)
大抵の場合は相続開始時が請求の起算点と考えて良いでしょうが、被相続人と遺留分権利者が疎遠で相続の事実を知らなかった場合や、遺産分割協議後に不平等な遺言が出てきた場合など、起算点が被相続人の死亡日(相続開始時)からずれることもあります。
また、相続開始から10年間という期限は不変なので、こちらに関しては10年が過ぎてしまうと権利が勝手に消滅してしまうことになります。
例えばAが平成18年3月30日に死亡したとして、疎遠にしていた子CがB・Dに遺留分を侵害されていることを知ったのが平成28年1月3日だった場合、平成28年1月4日~平成29年1月3日がCの請求権の存続期間になります。
ただ、遺留分の10年の期限にかかる平成28年3月30日以降は権利が消滅してしまうため、平成28年3月30日以降は遺留分減殺請求ができないというのがこの条文の考え方になります。
遺留分減殺請求は、遺留分権利者が侵害の相手方に対して「遺留分減殺の意思表示」を行うことでスタートします。この意思表示の方法に決まりはないので電話やメールなどで行うこともできますが、通常は後々の紛争に備えて内容証明郵便を利用して行うことが多いと言えます。
遺留分減殺の意思表示がなされると、当事者間での交渉が始まります。遺産分割協議などの際に併せて話し合いがなされることもあれば、弁護士等の代理人が請求者の代わりに相手方と話し合うこともあります。
この時点でお互い納得すれば遺留分相当の財産を渡して終了になりますが、なかなか決着がつかない場合には裁判所を交えての手続きに移行します。
遺留分に関する紛争は、裁判手続きの前に話し合いを行う「調停前置主義」が採られていますので、当事者同士の交渉が決裂すると、次は裁判所を交えての話し合い手続きである「遺留分減殺調停」に進むことになります。
遺留分減殺調停は、裁判官や調停委員という第三者を交えて遺留分の話し合いを行うものですが、当事者が一同に会して話し合いをするのではなく、個別面談のように当事者が裁判官等とやり取りを行い、それらの意見や状況を総合して和解案をまとめていく手続きです。
調停も上手く行かなければ最後は裁判(遺留分減殺の対象となる財産の引渡し又は移転登記請求訴訟)になり、通常の民事訴訟と同じように裁判所で裁判形式の手続きが進んでいくことになります。
以上が遺留分減殺請求の流れになりますが、遺留分減殺請求されたら絶対に遺留分を返さなければならないのかと不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、遺留分減殺請求がなされると、遺留分を侵害する限度で遺言や遺贈・贈与などの内容が無効になるわけですが、遺留分を渡さないことのリスクはどの程度大きいのか気になりますよね。
ここでは、遺留分減殺請求を拒否したい場合に絶対に気をつけていただきたい5つのことをご紹介いたします。
遺留分減殺請求がなされると、大抵の場合は内容証明郵便が送付されてきて遺留分減殺請求に気がつくことになります。
このとき、「面倒だ」「相手方と絶対に関わりたくない」「遺言があるのに何で請求されるのか」などと考える方が大半だと思いますが、内容証明郵便を無視することは避けた方が賢明です。
内容証明郵便は、あなたが無視したとしても相手方と郵便局に同様の手紙が保管されることになります。内容証明郵便を無視した場合、相手が話合いの余地がないとして訴訟や調停を申し立てる可能性が高いといえます。
話合いで解決可能な問題が法的紛争に発展してしまうこともありますので、通知を無視するのではなく慎重に対応して下さい。
遺留分減殺請求をされた場合、何よりも相手の請求内容を正しく理解することが重要になります。
具体的には、次の点をよく確認しましょう。
|
項目 |
チェックポイント |
|
相手方と被相続人の関係 |
|
|
相手方の請求内容 |
|
|
請求の根拠 |
|
|
自己の相続内容との比較 |
|
|
請求日 |
|
遺留分で混乱しやすいのが、遺留分は相続開始時の財産だけでなく、特別受益など一定の生前贈与も含めた全ての財産額から具体的な割合(価額)を算出するということです。
【参照元:遺留分算定の基礎となる相続財産の考え方】
被相続人の相続財産=(相続開始時の財産+相続開始前1年間になされた贈与+期限を問わず遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与+不相当対価の有償行為+共同相続人の特別受益)―全ての債務
例えば相続開始時の財産が200万円でも、共同相続人に1,000万円の特別受益があった場合には、これらを総計した1,200万円を被相続人の相続財産として考えて、そこから個別的な遺留分割合を掛け合わせることになるのです。
そのため、遺留分権利者が既に特別受益などによって充分な利益を得ていた結果、遺産分割等で遺産を取得できなかったからといって、遺留分侵害がなされているとも限らないのです。
逆に、あなた自身があまり遺産をもらえなかったとしても、既に得た特別受益などを考慮すると遺留分侵害をしているケースもありますから、現状を正しく理解する意味でも特別受益は特に注意しましょう。
遺留分を渡したくない場合でも、必ず一度は相手方と交渉しましょう。2・3の結果、自分が請求されるいわれがないのであれば、きちんとその旨を伝えたほうが逆恨みなどもされずに済みますし、勘違いされたまま調停や裁判に発展したほうが面倒です。
また、徹底抗戦するのであれば、相手方の態度や主張をしっかり理解したほうが戦いやすいので、相手方の出方を見ることは大切です。
4の際にハードルが高いと感じたならば、独力で頑張ろうとせず、専門家への相談も視野に入れましょう。正式に受任するかどうかは別として、「遺留分を請求されているが渡したくない、どういった交渉を行うのが無難なのか」といったことを相談するだけでも不安が和らぐと思います。
また、相手方が強引に交渉を持ちかけてくる場合には、専門家に相談している旨を伝えて待ってもらうこともできるでしょうから、一定の抑止力としての効果も期待できます。
専門家への相談自体はそこまで費用が高くありませんし、受任するかどうかは相談の際にすぐに決めなければならないわけではありませんので、まずは無料相談などを利用し、リラックスしてあなたの不安を打ち明けてみることをおすすめします。
相続は、いくら万全の準備をしていても関係者の気持ちや状況によって争いが生じることが珍しくなく、確実に円満に終わらせることは難しいのかもしれません。
ある程度相続人全員が平等になるように故人があらかじめ財産を分け与えていたり、相続人が不公平な相続に納得していた場合であっても、状況次第で大きな紛争が生じることは決して珍しくないのです。
遺留分減殺請求された場合には、多少面倒でもあなた自身で対策を取らざるをえない場面が出てきますので、面倒に感じたり負担を軽くしたい場合には、弁護士への相談がおすすめです。
|
遺留分減殺請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
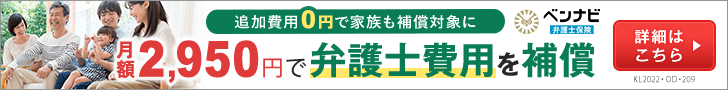
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


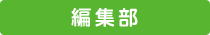
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。