決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
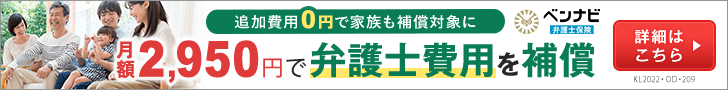
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


時間外労働(じかんがいろうどう)とは、その名の通り法律で定められた時間を超過して働くことです。しかし単純に時間外労働といっても、しっかりと理解しないまま働き続けることにより、さまざまな問題が生じてくることも多々あります。
今回はそんな時間外労働について詳しく見ていき、自分は正しく働けているのか、その分しっかりと手配を支給されているのかなどについて、考えていきましょう。
目次
まずはじめに、時間外労働の定義について簡単に解説していきたいと思います。
時間外労働とは、法定労働時間を超えて働いた場合に使われる言葉です。
法定労働時間とは国で定められた労働時間のことで、一日8時間、一週間で40時間とされています。
一日8時間の週6日勤務であれば合計で48時間勤務となりますので、8時間分が時間外労働となるということですね。
時間外労働というと、このように理解している方も多いのではないでしょうか。
「定時は9時から17時まで(休憩時間が一時間)と会社から言われたにもかかわらず、毎日18時まで働いている。それなのに、1時間分の時間外手当がもらえない。これ違法でしょ?」
といった感じです。
たしかに、就業規則に9時から17時までの勤務と書かれていれば、18時まで働いた分は時間外労働だと考えるのも自然ですよね。
しかし法律で割増賃金の発生する時間外労働とは法定労働時間を超える労働をいいます。
いくら会社の就業規則には9時から17時までの勤務(実働7時間)と書かれていても、法律で定められている一日8時間という法定労働時間を超えないかぎり、時間外労働とはみなされないのです。
残業をしたからといってその全てが時間外労働となるとは限らないのです。ただし、提示を超える労働について割増のない賃金は発生しますので、全く給与が発生しないわけではないことに注意しましょう。
残業による過労死も発生し、時間外労働は大きな社会問題となっています。会社側が労働者を不当に扱ったり、規定の労働時間を超えて働かせていたりなど、問題が山積している状態です。
それではここで、時間外労働とは本来どういったルールがあるのか、今一度しっかりと理解していきたいと思います。
時間外労働には、いったいどのくらいの上限があるのでしょうか?
過労死などの問題が多く発生するなか、この改善が常に求められてきました。
そもそもの話ですが、1日8時間、一週間に40時間を超える労働は、基本的に違法となります。
使用者は労働者に対し、時間外労働を課す場合にはしっかりと協定を結ぶ必要があるのです。
その時に必要となってくるのが、次に説明する「36協定」というものです。
労働基準法第36条には、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
(引用元:労働基準法第36条)
と記されています。
つまり、会社側が労働者に時間外労働させる場合には、この36協定を結ぶ必要があるということです。
それでは36協定とはいったいどういった仕組みなのか、解説していきます。
36協定とは時間外労働を認めるための制度であり、これを締結することによって、その時間外労働を
までとすることができます。
36協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出れば、本来であれば違法となる時間外労働も労働者に課すことができるということです。
逆に36協定を結ばずに時間外労働を労働者に課す行為は違法であり、悪質な場合は刑事罰が科せられることもあります。
また、36協定を結んでいるからといって無償で残業させられるわけもなく、使用者は労働者にしっかりと時間外手当を支払わなければなりません。
また、繁忙期など、月によっては業務が過多になる企業もありますので、そういった場合には「特別条項付き36協定」を締結することができます。
この特別条項付き36協定は簡単に言うと、
「特別で臨時的な事由がある場合に限り、通常の36協定を上回る時間外労働を課すことができる制度」
のことです。
臨時的な事由とは、
などが挙げられますね。
例えばこれらの繁忙期に、あらかじめ「今月は70時間の残業をします」という旨を特別条項に記載しおけば、その時間分の時間外労働が認められ、その残業は違法にはならないということになります。
またルールとして、この特別条項付き36協定を締結する場合には、
これらを36協定にしっかりと明記しなければなりません。
特別条項付き36協定が締結されたからといって好きなだけ残業をしていいかというとそうではなく、年に6回までと定められています。
つまりは、時間外労働の上限である45時間を一年中超えていいというわけではなく、回数制限がありますので、注意が必要です。
ご自身の時間外労働が発覚した場合、きちんと時間外手当を請求することが大切です。
誤解してしまいがちなのが、36協定を締結したからといっていくらでも残業を課すことができたり、また、時間外手当を支払わなくても良いというようなことです。
36協定を結んだとしても、使用者は労働者にしっかりと時間外手当を支払う義務がありますので、ここはきちんと理解しておきましょう。
それではここで、時間外労働をした際に支給される時間外手当の実際の計算例を解説していきます。
例:Aさんの会社の就業規則には、9時から17時の勤務(休憩時間が一時間)と書かれています。
ある時、Aさんは20時までの残業をしました。
このときに間違えてしまいがちなのは、17時から20時までの3時間を時間外労働として計算してしまうことです。
9時から17時まで勤務、休憩時間が一時間ということは、実働は7時間。しかし国が定める法定労働時間は、一日8時間です。
つまり、一日8時間を超えていない労働時間に関しては、その分の時間外手当は支給されないのです。
そのためAさんの場合、17時から18時までの1時間は法廷内の残業時間、18時間から20時までの2時間は法定外の残業時間として計算します。
この場合の計算は、
【Aさんの時給額×1時間(17時から18時までの労働)×1(割増にはなりません)+2時間(18時から20時までの労働)×1.25(時間外労働に適用される25%の割増賃金)】
となります。
時間外手当を請求する場合、まずはその証拠をしっかりと集めるところか始めましょう。
タイムカードの打刻確認、パソコンのログイン・ログアウト時間、会社の入退社の際のセキュリティの設定や解除の時間など、集められるところからは全て集めてください。
それをもって会社側に請求していくのですが、その際、
これらも合わせて記載しましょう。
そうすることで、より話し合いがスムーズに進んでいきます。
【関連記事】残業代請求の方法とは|手順や流れを解説
特殊な労働時間制度について、次の3つをご紹介します。
一日8時間、週に40時間という単純な労働時間制度は、すべての業種に当てはまるわけではありません。
時期によっては業務過多になったり、逆にまったく仕事の受注がない時期だったりと、業種によって働き方は様々です。
そういった企業にも柔軟に対応するために、以下に紹介する特殊な労働時間制度が存在しています。
変形労働時間制とは簡単に言うと、労働時間を一日単位ではなく、月や年単位で計算する制度のことです。
通常であれば、一日8時間を超える労働は時間外労働とみなされるのですが、企業によっては隔週で仕事量が変化することもあり、毎日この法定労働時間では対応できないというケースも出てきます。
その場合、例えば1週目は一日6時間勤務を5日間、2週目は逆に8時間勤務を5日間といったように、変形労働時間制を取り入れる企業も増えているんですね。
これを1ヶ月単位、もしくは1年単位で取り入れることができます。
1ヶ月単位の場合、その月の法定労働時間は以下の表のとおりです。
| 28日 | 160時間 |
| 29日 | 160.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
また、1年単位で変形労働時間制を取り入れる場合は、以下のような上限労働時間になっています。
| 365日 | 2085.7時間 |
| 366日 | 2091.4時間 |
では次に、フレックスタイム制についてご紹介していきます。
フレックスタイム制は自由に出退勤することが許される制度のことで、現代の働き方にとても合っている制度といえます。
主に労働者にとってメリットのある制度として、積極的に取り入れる企業も増えているようです。
自由な出退勤といっても、コアタイム(必ず出勤しなければいけない時間)があるので注意が必要です。
もう1点注意したいのは、たまたま一日だけ何時間残業したとしても、会社で決めた総労働時間を超えていなければ、時間外手当は出ないということです。
この総労働時間は、以下に収まるよう設定しなければなりません。
|
28日 |
160時間 |
|
29日 |
160.7時間 |
|
30日 |
171.4時間 |
|
31日 |
177.1時間 |
関連記事:フレックスタイム制とは|変形労働時間制の導入要件と残業代の考え方
最後に紹介するのは、裁量労働制に関してです。
裁量労働制とは、その名の通り、その人の考えによって労働時間を決めることができる制度のことです。
出勤の時間も退勤の時間も自由に決められるので、とても自由な働き方であるといえますね。
では、その人の好きなように毎日の労働時間が決められるのかというと、そういうことではありません。
裁量労働制を取り入れる際には、あらかじめどれだけ働いたかを決めておく、「みなし時間」が設定されています。
たとえば、みなし時間を一日7時間と設定している場合、たとえ3時間だけしか働かなくても、逆に10時間働いたとしても、労働時間は一律で7時間ということになります。
「こんなに働いているのになぜ7時間なんだ!」とか、「これしか働いていないのにラッキー!」といった従業員が入り混じっていると大きな問題にも繋がりかねないので、社内の労働環境をしっかりと加味し、みなし時間を決めていかなければなりません。
裁量労働制のルールとして、仮にみなし労働時間が1日8時間を超える場合には、36協定を締結し、当該超過分については時間外手当を支給しなければなりません。
休日出勤に関しても、週に一日の休みを取り入れること、また、休日の労働時間までみなすことはできませんので、休日の分の給与は別途支給する必要があります。
今回は、時間外労働とは何か、主にそのルールや間違いやすい事例について、解説してきました。
時間外労働と一口に言ってもその内容は意外と複雑であり、間違えて理解している使用者の方や労働者の方もいらっしゃるかと思います。
しかしここを間違って理解してしまうと、本来支給されるべき給与をもらえなかったり、また、知らない間に違反を犯してしまっていたりといったケースも多々起こりえます。
そんな状況を防ぐためにもこの記事をご覧いただき、果たしてその労働環境に違法性はないか、もう一度しっかりと見直してみましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
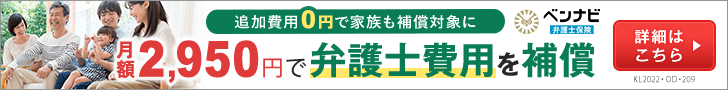
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


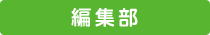
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。