決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


整骨院とは、国家資格を持った柔道整復師が、打撲、ねん挫などの症状に対して治療・施術を行う施設のことを言います。整骨院での治療は、医師の医療行為とは区別されており、医業類似行為という位置づけがなされています。
交通事故によるケガで、むち打ち症などと判断された場合、整形外科等の病院だけでなく、整骨院での治療・施術を行うことで症状が回復するケースもあります。
交通事故での受傷の治療のために病院に通院した際に「通院慰謝料」を加害者に対して請求することができます。この通院慰謝料額は、通院期間をベースに算定されます。では交通事故でのむち打ちなどの治療・施術のために整骨院に通院した期間も慰謝料額の算定に含まれるのでしょうか。
今回は交通事故で整骨院に通院した際の慰謝料の算定の方法と、慰謝料を請求する時の注意点を記載したいと思います。
目次
交通事故の受傷の治療のために整骨院に通院した期間についても、慰謝料の対象となります。慰謝料とは精神的な苦痛に対する補償のことをいいます。
慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますが、整骨院に通院した際には通院慰謝料を加害者に対して請求することができます。
通院慰謝料は通院期間や通院日数をもとに算出され通院期間や通院日数が多くなればそれに従い通院慰謝料も増額していきます。
交通事故の被害者は加害者に対して、受傷の治療にまつわる費用を損害賠償として請求することができます。病院での治療費に加えて、整骨院での治療費も損害賠償として請求可能です。整骨院の治療費等で請求できる費用は以下の通りです。
・電気療法
・手技療法
・温熱療法
・運動・ストレッチ
・鍼灸治療 (医師の同意書がない場合、認められないケースもある)
など
通院を行ったことの精神的な苦痛に対する補償を行う慰謝料ですが、苦痛の感じ方は人それぞれであるため、どのような金額にすべきか明確にならない方も多いのではないでしょうか。そのため慰謝料には、金額を定めるための「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準が設けられています。
自賠責保険は車やバイクの運転者であれば強制的に加入する保険です。自賠責保険の目的は事故被害者の保護にあります。自賠責保険での補償は、事故の被害者に対する最低限度の補償額に留まるのが特徴です。
自賠責保険基準での通院慰謝料は以下のAとBの小さい方の数字に4,200円をかけたもので算定されます。
A:通院期間の日数
B:実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
たとえば4月1日に事故に遭い、4月30日まで通院。実際の通院日数が10日だった場合、
A=通院期間の日数=30日
B=実通院日数×2=10×2=20
A>Bとなるので、この例のときの通院慰謝料は
通院慰謝料=4,200円×20日=84,000円
から84,000円となることが分かります。
任意保険は損害賠償額が自賠責保険の限度額を上回った部分をカバーするために、事故の加害者が加入している任意の保険会社のことをいいます。通院慰謝料の相場は各任意保険会社によって決められており、明確な数字は公開されていませんが、自賠責保険の補償額を少し上回る程度だと言われています。
また、自賠責保険では通院期間と実通院日数をもとに通院慰謝料額を算定しますが、任意保険基準では通院期間を用いて慰謝料額を決定するケースが多いです。
以下はあくまでも推定になりますが、任意保険の通院慰謝料の相場を記載しておきます。
表:任意保険の推定通院慰謝料(単位:万円)
| 通院期間 | 慰謝料額 |
| 1ヶ月 | 12.6 |
| 2ヶ月 | 25.2 |
| 3ヶ月 | 37.8 |
| 4ヶ月 | 47.8 |
| 5ヶ月 | 56.8 |
| 6ヶ月 | 64.2 |
| 7ヶ月 | 70.6 |
| 8ヶ月 | 76.8 |
| 9ヶ月 | 82 |
| 10ヶ月 | 87 |
弁護士基準とは別名裁判所基準と呼ばれるものです。過去の裁判の判例をもとに、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しています。実際の裁判でも慰謝料算定の基準とされており、その他の2つの基準に比べて最も客観性が高い基準です。また慰謝料額も最も高くなっています。
弁護士基準での通院慰謝料も通院期間をベースに慰謝料額を算定します。ただし通院は一週間に少なくとも2回程度を標準にしています。実際の通院日数がそれより多かったり、少なかったりした場合は慰謝料額が増減します。また受傷の状態によっても慰謝料額が増減します。
以下に弁護士基準での通院慰謝料額を記載しておきます。
表:弁護士基準での通院慰謝料額(単位:万円)
| 通院期間 | 通院慰謝料額 |
| 1ヶ月 | 16~29 |
| 2ヶ月 | 31~57 |
| 3ヶ月 | 46~84 |
| 4ヶ月 | 57~105 |
| 5ヶ月 | 67~123 |
| 6ヶ月 | 76~139 |
| 7ヶ月 | 84~153 |
| 8ヶ月 | 90~165 |
| 9ヶ月 | 95~174 |
| 10ヶ月 | 100~182 |
交通事故で請求できる慰謝料は入通院慰謝料だけではありません。
他にも後遺障害慰謝料等も存在します。
交通事故の慰謝料全般の相場を知っておくことで、具体的にどれくらいの金額を相手に請求できるのかの目処をつけることが出来ます。
一度下記の記事を読んで、具体的な交通事故慰謝料全般の相場を確認しておきましょう。
また、あなたの交通事故被害に対して、具体的にどれくらいの慰謝料を請求できるのかは実際に計算することで判明します。
相場はあくまでも全体的な平均に近しいものにすぎません。
具体的にあなたの場合どれくらいの慰謝料金額を請求できるかを知ることで、加害者に対しても客観的な根拠をもって慰謝料請求の主張を行うことが出来るようになります。
下記の記事から、実際にあなたの慰謝料請求可能な金額を計算してみると良いでしょう。
通院慰謝料を適切に受け取るために、以下の点には注意してください。
交通事故事件のほとんどが示談で解決されています。
この際加害者から被害者へ支払われる損害賠償額は双方が合意していればどのような額でも問題はありません。示談は加害者の加入する任意保険会社と被害者が交渉を行うことになります。そして保険会社は営利企業であるため示談の際に支払う損害賠償額もできるだけ少なくすることを望んでいます。
保険会社は示談交渉のプロであり、法律的な知識も豊富に持ち合わせています。
そのため被害者との情報格差から、妥当な通院慰謝料額より低い額を提示してくる場合も考えられます。ご自身の通院慰謝料額が不当に少ない額を提示されていないか、注意する必要があります。
交通事故のケガの治療中に、保険会社から早い段階での治療の終了や症状固定(治療したにもかかわらずケガの症状の回復が今以上に見込まれないこと)を打診してくるケースがあります。
これは治療にかかる費用を保険会社に損害賠償として請求することが出来ることを原因としています。治療の終了や症状固定が早い段階で決定すれば、以後通院の必要があったとしてもすべて自費になってしまいます。
治療の終了や症状固定は保険会社が決めることではなく、医師が決めます。保険会社から打診があっても、医師がまだ治療による回復が可能であると判断している場合もありますので、医師と十分にコミュニケーションをとりながら、治療終了や症状固定を決定するようにしてください。
症状固定となったあとにも症状が残っている場合、後遺障害の認定を受けることが出来れば後遺障害慰謝料、逸失利益などを損害賠償として請求することができ、損害賠償額の増額が見込めます。
後遺障害の認定には申請をしなければなりません。申請の方法は「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。それぞれの詳しい内容は「事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ」「被害者請求とは|交通事故の被害者が適正な慰謝料獲得のために知るべきこと」に記載していますので、参考にしてください。
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所で行われます。自賠責損賠調査事務所での認定は医師の記載した「後遺障害診断書」とその他資料により行われます。
後遺障害診断書は医師のみが書くことができ、整骨院の柔道整復師では書くことが出来ません。また後遺障害診断書には初診からの症状の推移を記載しなければなりません。
そのため整骨院ばかりに通院している場合、後遺障害として認定される症状であっても整骨院等の病院への通院が少ない場合適切に認定を受けられなくなります。
整骨院に通う際に示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて記載したいと思います
示談交渉は被害者と加害者側の保険会社が行いますが、被害者側が弁護士基準での通院慰謝料を望んでも保険会社は受け入れてくれない場合が多いです。
弁護士基準での通院慰謝料獲得を望むのであれば、弁護士への示談交渉の依頼を強くお勧めします。また慰謝料には通院慰謝料以外にも後遺障害慰謝料もあります。後遺障害慰謝料にも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」が存在し、弁護費基準が最も高額になっています。
弁護士に示談交渉をすることで、通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料の増額も見込むことができます。
示談を行う際には保険会社とのやり取りや、必要書類の収集が必要になります。弁護士に示談交渉の依頼をしておけば、保険会社とのやり取りも行ってくれますし、必要書類の収集も代行してくれます。
そうすれば示談交渉にかかる手間や時間そして精神的な負担等を軽減することができ、受傷の治療に専念することができます。
後遺障害の認定は医師の作成する「後遺障害診断書」とその他必要資料により行われます。但し医師は治療をするプロではありますが、後遺障害認定に関しては詳しくないケースがあります。
後遺障害として認定されるためには、検査等を行う必要がありますが、治療に必要な検査でない場合、医師が検査を行わない可能性があります。弁護士に示談を依頼していれば、後遺障害認定に必要な検査や「後遺障害診断書」の記載内容について医師に適切に提言をすることができます。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼することには、他にもメリットが沢山あります。
メリットを知ってから弁護士に依頼するかどうか判断してもよいでしょう。
整骨院に通院した場合の慰謝料や注意点についてご理解いただけたでしょうか。
整骨院に通院している場合、通院回数や通院期間が多くなったり長くなる場合もあり、その分損害賠償額も増加することから「妥当な診察かどうか」について保険会社から言及されるケースもあると聞きます。少しでも保険会社とのやり取りで疑問に思うことがあった場合は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


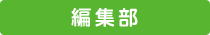
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。