決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく利用されている書式ではありますが、一般の方が作成するケースはあまりありません。
遺産分割協議証明書も遺産分割協議書も、文書の持つ効力は同じなので、相続の事情に応じて賢く使い分けて行けると非常に便利かと思いますので、今回はこれらの違いや遺産分割協議証明書の作り方などについて、詳しくご紹介していきます。
|
遺産分割について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の大きな違いは、署名捺印する相続人の数です。遺産分割協議書は、「相続人全員が合意してこのような遺産分割をしましたよ」という証明書のようなものなので、必ず相続人全員の署名捺印が必要になります。
これに対して、遺産分割協議証明書は「相続人全員が合意して遺産分割した結果、このような内容になったことを私は証明しますよ」という書類なので、相続人ごとに分割結果に従った個別の内容で作成し、それぞれの相続人が署名捺印するということになります。
ここでは、遺産分割協議証明書の概要についてご紹介したいと思います。
遺産分割協議証明書のメリットは、相続人ごとに個別の署名捺印をするだけで良いという手続きの簡便さにあります。
もちろん、大元となる遺産分割協議について、全員の合意があることが前提条件になりますが、遺産分割協議は必ず相続人全員が一堂に会して行わなければならないという性質ではありませんから、電話などで合意が取れていれば、それぞれの相続人の相続分に応じた書類を作ってそれに署名捺印してもらうだけの遺産分割協議証明書は非常に役に立ちます。
遺産分割協議書を作成するとなると1通の書類に相続人全員の署名捺印が要求されるので、相続人が多数いる場合や各地に点在している場合には作成自体が難しくなります。
相続人全員の署名捺印を集めるため郵送で書類を回していると、その途中で紛失してしまう危険もありますし、手続き完了までかなりの時間を要することになりますので、このようなケースでは遺産分割協議証明書の利用がおすすめです。
相続の際、相続人が1人しかいない場合や遺言書通りの相続が行われる場合には遺産分割協議は必要ありませんから、各種手続において遺産分割協議証明書等の書類を添付する必要はありません。
しかし、そうでない多くのケースでは、金融機関や登記手続きにおいて、遺産分割協議証明書等の添付が必要になりますので、ここではどういった場面でこれらの書類が必要になるのかをまとめてみました。
相続が狭い範囲で円満に完結し、相続人全員が互いの素性を良く知っているような場合でも、それを相続人以外の他人が判断するのは困難です。相続は被相続人の財産処分を伴う手続きなので、公的機関や金融機関は一層慎重にその妥当性を判断することになります。
すなわち、これらの機関が相続手続きの際に遺言や遺産分割協議証明書・遺産分割協議書の提出を求めるというのは、これらが「第三者に客観的に相続の内容を証明する書類」になるからなのです。
被相続人の戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等が必要になるのも同様の理由で、「誰の相続で、誰が相続人になって、相続内容はどのようなものなのか」を第三者が判断する資料になりますから、面倒でもきちんと所定の書類を揃えて手続きをしなければなりません。
相続手続きにおいて、遺産分割協議証明書や遺産分割協議書が必要になる手続きは、主に下記のものになります。
遺言書がある場合にはこれらの書類が不要になることもありますが、遺言書と異なる内容での遺産分割を行った場合には協議書や協議証明書が必要になりますので、きちんと把握しておきましょう。
被相続人から不動産を相続したり処分して現金化して相続を進める場合には、一度不動産の名義変更をすることになります。
この名義変更に伴う登記を「相続登記」と呼びますが、法務局へ登記申請する際には遺言書や遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)を提出する必要があります。
金融機関の預金相続手続きをする場合、相続財産を誰が取得するのかについては厳密な審査が行われるため、遺言書または遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)の提出が必要不可欠です。
金融機関同様、証券会社での被相続人名義の株の名義変更手続きにも遺言書または遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)が必要です。
被相続人名義の自動車を相続したり処分する際には、必ず名義変更が必要になります。この名義変更手続きには、一般的には遺言書または遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)の添付が要求されます。
ただし、自動車の評価額が100万円以下の場合は遺産分割協議書等に替えて自動車の査定書と申立書で手続きを進めることができますが、わざわざ有料の査定を頼むよりは遺産分割協議書等を利用した方が良いでしょう。
相続税の申告の際にも、基本的には遺言書または遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)の添付が必要です。
ただし、申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合は、法定相続があったものとして相続税の申告をすることになるので、この場合は遺産分割協議が調った後で修正申告を行うことになります。そのため、このようなケースでは最初の申告の際には協議書等の添付は必要ありませんが、修正申告で必要になると覚えておくと良いでしょう。
以上が遺産分割協議証明書についての各種の知識になりますが、ここからは遺産分割協議書や遺産分割協議証明書の実際の作り方についてご紹介いたします。
どちらの書式を利用しても法的効果に変わりありませんので、相続人の状況に合わせて適宜方法を選択していただければ良いかと思います。
|
遺産分割協議書 平成29年4月2日に死亡した被相続人アシロ太郎(東京都新宿区西新宿○○番地)の遺産について,同人の共同相続人アシロ花子・アシロ一郎・アシロ二郎の全員によって分割協議を行った結果,以下の通り各相続人で遺産を分割し,相続することに決定した。 1.相続人アシロ花子が取得する財産 (1)東京都新宿区西新宿○○番地 居宅 1棟 面積 165.02平方メートル (2) 有価証券 被相続人が,△△証券○○支店内特定口座に所有していた有価証券のうち,公募債投資信託(以下、MMFとする)450万口を除いたすべての債権 (3) 預貯金 普通預金 361,655円(△△銀行○○支店) 定期預金 3,145,796円(○○郵便局) 2.相続人アシロ一郎が取得する財産 (1) 土地 被相続人が所有していたすべての土地 (2) 有価証券MMF 1,000,000口(△△証券○○支店) (3) 預貯金 普通預金 1,340,336円(△△銀行○○支店) 定期預金 5,000,000円(○○郵便局) (4) その他の財産 特約還付金 証書番号 1234567 614,592円 同 証書番号 2345678 409,120円 入院特約 合算 378,356円 (以上2口すべて○○郵便局) (7) 保険契約に関する権利 建物共済 証書番号 5678(○○共済○○支店) 養老生命共済 証書番号 6789(同上) (8) その他の権利 電話加入権 1基 0000-00-0000番 普通乗用車 1台 新宿○○ あ1234 日産○○ 3.相続人アシロ二郎が取得する財産 (1) 有価証券 MMF 1,000,000口(△△証券○○支店) (2) 預貯金 普通預金 4,605,465円(△△銀行○○支店) 定期預金 10,110,634円(○○銀行○○支店) 同 10,139,043円(△△銀行○○支店) 4.相続人アシロ花子が負担する債務 医療費の未払金 220,455円 6.相続人アシロ一郎が負担する債務 (1) 公租公課 132,152円 (2) 葬式費用 2,780,120円 上記の通り,相続人全員による遺産分割協議が成立したので,これを証するため,本書3通を作成し,署名押印の上,各1通宛所持する。 平成29年4月30日 東京都新宿区西新宿○○番地 相続人 アシロ花子 印 東京都三鷹市下連雀○○番地 相続人 アシロ一郎 印 茨城県東茨城郡茨城町○○番地 相続人 アシロ次郎 印 |
遺産分割協議書を作成する際には、きちんと以下の点を記載しましょう。
そして、文書の最後には相続人全員が署名捺印し、複数枚にわたる場合はきちんと割り印をします。協議書を作成したら相続人全員が各一通ずつ所持するようにするのが後日の紛争防止の意味でも良いでしょう。
もし、自分で遺産分割協議書を作成することが難しい場合は、弁護士に依頼することも可能です。
遺産分割協議証明書の作成の際には、必ず「相続人全員の合意のもと遺産分割協議が成立したことを証明しますよ」といった内容を記載することになります。
作り方としては2パターンあり、各相続人が自己が取得した分の相続財産について証明するというタイプと、遺産分割協議全体の成立について証明するというタイプがあります。
|
遺産分割協議証明書 平成29年4月2日に死亡した被相続人アシロ太郎(東京都新宿区西新宿○○番地)の遺産について,同人の共同相続人アシロ花子・アシロ一郎・アシロ二郎の全員によって4月30日に分割協議を行った結果,以下の相続財産をアシロ花子が取得したことを証明する。 1.相続人アシロ花子が取得する財産 (1) 東京都新宿区西新宿○○番地 居宅 1棟 面積 165.02平方メートル (2) 有価証券 被相続人が,△△証券○○支店内特定口座に所有していた有価証券のうち,公募債投資信託(以下、MMFとする)450万口を除いたすべての債権 (3) 預貯金 普通預金 361,655円(△△銀行○○支店) 定期預金 3,145,796円(○○郵便局) 2.相続人アシロ花子が負担する債務 医療費の未払金 220,455円 平成29年5月10日 東京都新宿区西新宿○○番地 相続人 アシロ花子 印 |
|
遺産分割協議証明書 平成29年4月2日に死亡した被相続人アシロ太郎(東京都新宿区西新宿○○番地)の遺産について,同人の共同相続人アシロ花子・アシロ一郎・アシロ二郎の全員によって分割協議を行った結果,以下の通り各相続人で遺産を分割し,相続することに決定した。 アシロ花子は,下記内容での遺産分割協議が4月30日に成立したことを証明する。 1.相続人アシロ花子が取得する財産 (1) 東京都新宿区西新宿○○番地 居宅 1棟 面積 165.02平方メートル (2) 有価証券 被相続人が,△△証券○○支店内特定口座に所有していた有価証券のうち,公募債投資信託(以下、MMFとする)450万口を除いたすべての債権 (3) 預貯金 普通預金 361,655円(△△銀行○○支店) 定期預金 3,145,796円(○○郵便局) 2.相続人アシロ一郎が取得する財産 (1) 土地 被相続人が所有していたすべての土地 (2) 有価証券 MMF 1,000,000口(△△証券○○支店) (3) 預貯金 普通預金 1,340,336円(△△銀行○○支店) 定期預金 5,000,000円(○○郵便局) (4) その他の財産 特約還付金 証書番号 1234567 614,592円 同 証書番号 2345678 409,120円 入院特約 合算 378,356円 (以上2口すべて○○郵便局) (7) 保険契約に関する権利 建物共済 証書番号 5678(○○共済○○支店) 養老生命共済 証書番号 6789(同上) (8) その他の権利 電話加入権 1基 0000-00-0000番 普通乗用車 1台 新宿○○ あ1234 日産○○ 3.相続人アシロ二郎が取得する財産 (1) 有価証券 MMF 1,000,000口(△△証券○○支店) (2) 預貯金 普通預金 4,605,465円(△△銀行○○支店) 定期預金 10,110,634円(○○銀行○○支店) 同 10,139,043円(△△銀行○○支店) 4.相続人アシロ花子が負担する債務 医療費の未払金 220,455円 6.相続人アシロ一郎が負担する債務 (1) 公租公課 132,152円 (2) 葬式費用 2,780,120円 平成29年5月10日 東京都新宿区西新宿○○番地 相続人 アシロ花子 印 |
遺産分割協議証明書の場合は、どちらの書き方を選択しても、必ず下記の内容を記載します。
そして、文書の最後には当該相続人が署名捺印をします。遺産分割協議証明書についても相続人の人数分複製し、それぞれが所持しておく方が無難ですが、登記などで全員分の協議証明書が必要でなければ、各自が自分の分だけ複製して所持しておくというのでも良いでしょう。
遺産分割協議証明書が送られてきたら、内容を確認し、相違なければ署名捺印して代表となる(証明書を取り纏めている)相続人へ返送するというのが一般的な流れです。
もし内容に不備があったり、協議した内容と異なっている場合には、直ちに他の相続人へ確認を取り、署名捺印を保留します。ここで安易に署名捺印してしまうと、その通りの遺産分割が成立してしまうことになりますから、少しでも疑問がある場合には慌てて署名捺印せず、落ち着いてきちんと確認を取るようにしましょう。
一度、遺産分割が成立してしまうと、やり直しを行うことは困難になります。
自分にとって納得のいかない分割内容だった場合は、弁護士に証明書の内容が妥当かどうか確認してもらうことをオススメします。
遺産分割協議書はよく耳にしますが、遺産分割協議証明書を目にする機会はあまりないと思いますので、このような書類が送られてきたら不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、本記事の通り、書式に若干の違いはあるものの、内容は遺産分割協議の結果をまとめたものになりますので、協議証明書の内容に不備がなければ安心して署名押印手続きを行ってください。それでも心配であれば、弁護士等の無料相談などを利用して、一度協議証明書に目を通してもらうのがおすすめです。
|
遺産分割について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


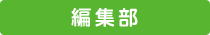
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。