決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
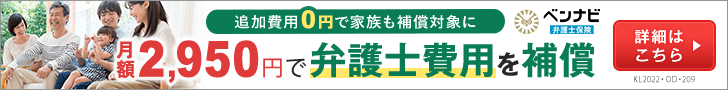
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


50代女性のAさんは、遺産相続問題に頭を悩ませています。3ヶ月ほど前、80歳の父親が亡くなりました。会社を経営していたこともある父だけに、Aさんは死後遺産の受け取りを希望し、「アテに」していたのですが…。
ところが父の残した遺言書には、「内縁の妻に全てを譲る。娘にはビタ一文渡さない」と書かれていたのです。Aさんはこの事実に大きなショックを受けていまいます。
父親はAさんが20歳のときに離婚。その後、結婚はしていませんでしたが、内縁関係にある女性が存在し、一緒に暮らしていたそうです。
Aさんは父親が気まずい空気にならないよう、敢えて距離を取っていたそうで、そのうち自分にも家庭ができたため疎遠になっていました。
父親が病魔に倒れてからも、なんとなく気まずさを感じていたAさんは、面会に行かずじまい。結局、容態が急変し、帰らぬ人となってしまいます。
葬儀のあと、遺産相続について話し合うと、内縁の妻の代理人弁護士が遺言書を取り出し、「全て内縁の妻に譲ると書いてある。したがって、あなたに遺産相続の権利はありません」と告げられてしまいました。
身の回りの世話などをしていなかったため、内縁の妻が遺産を受け取ることは致し方ないと感じているAさんですが、じつの娘にもかかわらず全く受け取ることができないことに大きな不満を持っています。
じつの娘でも、遺言書に「受け取らせない」と書かれていたら、遺産を手にすることは不可能なのでしょうか? あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
高野倉弁護士:「原則として、遺言は有効です。遺言に従えば、娘さんに相続分はありません。
ただし、娘さんは、遺留分侵害額請求をすることができます。平成30年の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていた制度です。娘さんは、遺産の2分の1について遺留分(総体的遺留分)を持ちます(民法1042条1項2号)。
娘さんの他に相続人がいないのであれば、娘さんは、遺産全体の評価額(正確には、民法1043条に基づいて算出された「遺留分を算定するための財産の価額」)の2分の1にあたる金額を遺留分侵害額として請求することができます。
また、内縁の妻Aが同意するなら、遺産分割協議によって、遺言とは異なる内容で遺産を分けることもできます(内縁の妻Aは本来相続人ではありませんが、遺言によって全財産の遺贈を受けた包括受遺者であり、民法990条によって相続人と同視されることになるので、遺産分割協議に参加する資格があります)。
なお、Aが内縁の妻とはいえず、単なる不倫相手であり、不倫関係を継続する目的で作成された遺言については、公序良俗に反し無効とされる余地があります」
弁護士に相談を
Aさんにとっては納得がいかないかもしれませんが、原則としては遺言書の内容が尊重されなければいけないようです。
「どうしても納得できない」場合は、弁護士と話し合い対応を協議することが最善策と言えそうですね。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
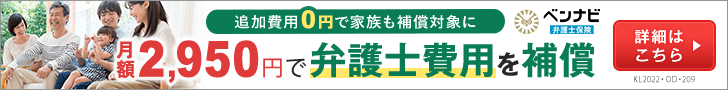
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


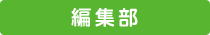
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。