決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


症状固定(しょうじょうこてい)とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことであり、後遺障害等級に認定してもらうために必要な条件です。この症状固定については、医師と患者である被害者で判断することが適切だとされています。
交通事故によって深刻な傷病を負った被害者は入院や通院を続けて治療してもらいますが、治療を継続しても症状が良くも悪くもならない状態で残ってしまうことがあります。
症状固定について保険会社からの要求で決めてしまうと、補償を受けられなくなるなど思わぬトラブルを引き起こす可能性もあるので、症状固定を決める上での注意点を知っておきましょう。
目次
治療を続けても回復しない症状に対し被害者は、慰謝料をもらうために症状固定を決めてもらってから、等級認定の申請手続きへ移ることになります。実際、症状固定について加害者側の任意保険会社より「症状固定ではないか?」と確認されることが多いようですが、症状固定を正しく決めるには医師と被害者の話し合いが必要だとされています。
診断している担当の医師が被害者の症状や治療経過を一番良く知っているので、医師の判断は確かなものです。しかし、医学的所見だけでなく被害者本人の自覚症状も合わせて確認するべきです。
担当の医師より症状固定の宣告を受けても、被害者は自分の症状をよく確認して医師と相談することが大事です。医師の診断も尊重するべきですが、痛みが残っていたり違和感があったりする場合は、その自覚症状を正直に申し出て本当に症状固定の状態なのかどうか検討するべきでしょう。
また、被害者側から症状固定の確認を担当の医師にする場合、同時に後遺障害診断書の作成依頼もすることになります。仮に医師からも症状固定であると判断された際は、後遺障害診断書に症状固定日を医師に記入してもらうほか、その他の記入欄である自覚症状や他覚症状、後遺障害の詳細なども併せて書いてもらいます。
参照元:「後遺障害診断書の書き方」
被害者が気をつけるべき点は、加害者側の任意保険会社による症状固定日確定の催促です。早めに症状固定を決める理由として、被害者側は多額の後遺障害慰謝料を獲得するための等級認定の申請に移行したいことが考えられますが、保険会社側の目的は全く別で、被害者に対する治療費の支払いを打ち切る可能性があります。
加害者側の任意保険会社が症状固定を迫るのは、症状固定がされると傷害に関する賠償期間が終わることと関係しています。症状固定のタイミングで被害者への治療費の支払いをしなくてもよくなるので、任意保険会社は症状固定を持ちかけてくるケースが実際にあり、極端な場合は治療費を打ち切ると宣告することもあり得ます。
実際には症状固定に達していないのに、保険会社より「症状固定であるため治療費の支払いを止める」と告げられた場合は一度保険会社に確認して、被害者側が納得出来ない状況であれば弁護士に相談した方が良いでしょう。被害者自身でも直接保険会社と話し合うこと可能ですが、専門的な知識を使って保険会社と交渉する必要があるため、弁護士に依頼するのがより確実だと思われます。
保険会社より治療費の打ち切りを受けたことで病院に通わなくなると、治療をする必要がない状態だと思われ、それが症状固定である証拠になってしまう恐れもありますので、保険会社の言いなりにならず、治療の必要がある場合は通院を継続しましょう。
また、上記で取り上げたように症状固定後は治療費の支給が無くなりますが、痛みや痺れが残っている場合は自己負担で通院することも決して無駄なことではありません。症状固定後の通院頻度が症状の重さを証明することに繋がり、適切な後遺障害等級の認定を受けるための有益な証拠になり得ます。費用的な負担はありますが、症状固定後も通院する必要があると被害者が感じたなら、病院で診察や検査を受け続けた方が良いでしょう。
これまでお話しました症状固定について、実は『医学上の症状固定』と『法律上の症状固定』の両方の意味を合わせて取り上げていました。なので、2種類の意味に分類して症状固定の定義を改めて確認していきましょう。
医学的な意味での症状固定は、治療を継続しても症状の程度はある一定で留まり、回復も悪化もしないことを示します。薬を服用したりリハビリを受けたりすることで多少は良くなるものの、完全には回復しない状態のままであることです。
法律的な意味での症状固定は、治療費や入通院慰謝料などの支払請求を終えて、症状固定後で可能となる後遺障害等級認定の申請へ移行することを示します。症状固定になることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの請求が可能になりますが、傷害部分とされる治療費や休業損害の請求はできなくなってしまいます。
『治療費の打ち切りを目的にしている可能性がある』の項目で説明した任意保険会社側による症状固定の強制は、医学上の観点ではなく法律上の問題と関係していることになります。
医学上、及び法律上の症状固定について図で表すと下記の通りになります。
交通事故が発生して受傷してから症状固定になるまで、通常は半年以上の経過で症状固定になる場合が多いですが、症状の種類によっては長期間になる場合もあります。
むち打ち症に関してはレントゲンやMRI写真での立証が難しい障害なので、後遺障害等級認定の条件において治療期間や通院の日数が重要になります。なので、後遺障害として認定されるためには半年以上の通院・治療期間が必要です。
骨折については、修復されても変形していたり短縮していたりする場合が後遺障害としての条件になり、症状固定まで半年もかからない場合もありますが、骨がくっつくことである骨癒合(ほねゆごう)まで時間がかかったり、プレートやスクリューなどを取り外す場合だと1年~2年程度かかることもあります。
醜状(しゅうじょう)とは、けがの痕や傷などが身体に残った状態を言います。通常は傷が治ってから半年の経過で症状固定になりますが、レーザー治療などで傷跡を改善する必要がある場合、段階的に複数回照射することで治療期間が長くなりますので、症状固定まで2年以上かかることもあります。
脳の状態やリハビリの進捗を基に脳機能の回復状況を確認することになりますが、リハビリによる改善の効果が出るまで1年~2年程度はかける必要がありますので、症状固定もそれだけ長期間になると思われます。
上記の通り症状固定の条件が決められていますが、医師と被害者で相談して決めた症状固定日を後遺障害診断書に記載して申請しても、裁判で加害者側の任意保険会社と症状固定日をめぐって争いになるケースもあります。
症状固定日を最終的に判断するのは裁判所になります。裁判所は基本的には医師の判断を尊重しますが、後遺障害診断書に書かれた症状固定日は確実に保証されるものではありません。場合によっては保険会社の判断を採用することも考えられます。
例えば、実際には症状固定まで1年治療したのに、保険会社が事故発生から症状固定まで9カ月しか経過していないとの判断が裁判で認められた場合、3カ月分の治療費は被害者の自己負担になってしまいます。このように被害者が不利益を被る可能性もゼロではありません。
裁判所では医師の見識に加え、下記の要素から医師が決めた症状固定時期が妥当かどうかを検討することになります。
被害者の症状に関する内容や医学的な証拠を基準に症状固定日の是非が確認されますので、被害者側から症状固定の希望があっても医師と相談して慎重に決めるようにしましょう。
症状固定の適切な決め方について解説しましたが、症状固定は保険会社より促されて決めることではなく、担当の医師と話し合って決定することだと覚えておきましょう。
症状固定が決まれば後遺障害等級認定の申請と慰謝料の請求が可能になります。被害者の精神的苦痛に対する補償を受けるためにも、医師の専門的な判断と被害者自身の意思で症状固定を確実に決めるのが重要となります。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


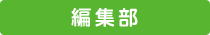
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。