決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
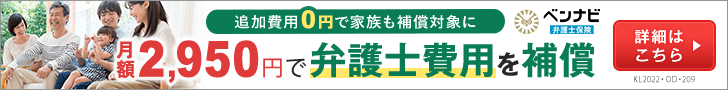
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


更正処分(こうせいしょぶん)とは、納税者の提出した申告書の内容に誤りがあると判断された際に求められる修正申告(誤りを修正し申告書の再提出をすること)に応じなかった場合、税務署が納税額の修正もしくは決定をする手続きのことです。
税務署「納税申告書の内容に間違いがあるから訂正して再提出してねー」
納税者「間違っている部分なんかないし無視しよう」
税務署「間違いを修正した納税額を出したので確認してください!」
簡略化するとこのようなイメージになりますね。更正処分とは税務署が申告書の不備に納得していない納税者に対して誤りの指摘を行う通知なのです。
『処分』という単語を見ると悪い印象を抱くかもしれないですが、あくまで『税務署からの通知』なので、更正処分を受けたからといって罰金が課されたり、犯罪行為として扱われるわけではないのでご安心ください。
ちなみに、納税者に修正申告に応じてもらえない際に税務署が更正処分を通知できるのは原則上5年(納税者の申告に虚偽があった場合は7年)までと定められています。
当記事では更正処分についての解説とそれを活用する利点や流れについてご紹介しますので、更正処分とは何かを調べている場合は参考にしてみてください。
税務署からの最初の指摘で求められる修正申告、それを拒否した際に通知される更正処分ですが、支払いを求められる納税額に違いはありません。
唯一違うのは不服の申し立てを出来るかどうかという点のみです。
修正申告は納税者自ら申告するものなので、一旦申請をすると申告書の誤りに納得したと見なされ訂正不可になりますが、更正処分の場合は税務署からの処分のため納得いかなければ不服申し立てができる権利が認められています。
上記の通り、税務署が訂正を求めてきた納税額に納得いかない場合に不服申し立てを行い、税務署からの要求が不当だと抗議する権利を確保できる点が更正処分を受けるメリットです。
税務署からの修正申告の要請がしつこく対応で時間が取られ不服申し立ての手続きでも時間がかかる、その『手間』が更正処分を受けるデメリットになります。
更正処分を行うということは不服申し立てをされる可能性が高いため、税務署はその二度手間を避けるため、修正申告をさせようと必死に要請をしてくるので、それを手間に感じ修正申告が行われるケースが多いそうです。
などなど、他にも様々な要請に対応していく必要があります。
しかし要請に納得していないのに修正申告に応じてしまうと、もう異議を申し立てることが出来なくなるため、どんなに手間がかかる場合でも税務署の要請に不服申し立てをしたいのならば屈せずに戦っていきましょう。
税務署から受け取った更正処分に不服がある場合は3カ月以内に下記の2通りいずれかの対処を選択して対応を行いましょう。
初めに税務署長等に対する再調査の請求を選択してその結果に納得できない場合は、再調査の請求についての決定を受け取った翌日から1カ月以内に国税不服審判所長に審査請求を行います。
そしてその審査結果にもまだ納得できない場合は、その裁決があったと知った日から6カ月以内に裁判所へ訴訟を提起することが可能です。
ただ上記されている期限を過ぎてしまうと、税務署から受け取った更正処分で指定されている納税額に対して異議を申し立てる権利を失ってしまうので、可能な限り早め早めに対処するようご注意下さい。
更正処分の受け取りは税務署からの修正申告の提出申請に納得できない際にとられる手段の1つです。
税務署から訂正の要求をされても正当な主張で異議を主張し続けていく自信があるのならば、あえて更正処分の受け取りも選択肢の1つと受け入れてみるのはいかがでしょうか。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
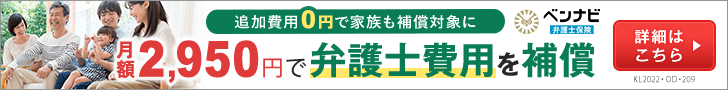
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


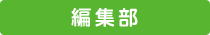
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。