決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


取消訴訟(とりけしそしょう)とは行政訴訟の一種であり、抗告訴訟(こうこくそしょう)に分類されるものです。具体的には、国や地方公共団体などの行政庁による処分や裁決などの行為を取り消す訴えを意味します。
一般的な民事事件や刑事事件と異なり、行政事件に関する制度はあまり世間に浸透していませんが、取消訴訟は懲戒処分や税務処分を受けた時に知っておくべき手続きであるため、法律上の規定や訴訟提起における注意点などを把握しておいた方が良いでしょう。
今回は取消訴訟を提起する目的と、取消訴訟に関連する行政不服審査制度を併せて説明していきたいと思います。
|
取消訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
まずは取消訴訟の概要について、提起する目的を含めて以下で解説していきます。専門的な用語になりますが、取消訴訟を説明する上で取消訴訟の排他的管轄という言葉が重要になります。
取消訴訟は以下の図で示されている通り、行政訴訟(または行政事件訴訟)の一種になります。
主観訴訟とは個人の権利や利益を保護するための訴訟を意味し、抗告訴訟は冒頭で説明した通り、国や地方公共団体などの行政庁において、国民を法律的に支配する権利(公権力)を行使することに対する不服を意味します。
取消訴訟は名前の通り、行政庁から個人の権利に影響を与える行為を取り消すことを目的とします。その行政庁の行為というのは主に以下の2種類へと分類されますが、具体的な事例については次項で取り上げていきます。
|
処分の取り消しの訴え |
国や地方公共団体などの行政機関(行政庁)が行った処分を取り消すため、裁判所へ訴えます。 |
|
裁決の取り消しの訴え |
行政機関が行った裁決・決定などを取り消すため、裁判所へ訴えます。 |
行政事件については民事事件や刑事事件と異なり、違法性の有無における判断が非常に難しく、裁判所などの専門機関で慎重に審理を進めることが求められますが、取消訴訟の排他的管轄という考え方が浸透しており、行政訴訟以外の手続きでは行政処分(または裁決)の取消しができないという制度になっています。
したがって、民事訴訟では行政処分の法的な効果を否定することはできない、ということになり、以下の行政事件訴訟法第3条で規定されている取消訴訟が唯一、行政処分を取消すことができる手段だといえます。
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
引用元:行政事件訴訟法 第3条 1項~3項
実際に取消訴訟を提起して裁判で争った場合、和解を除いて裁判所から下される判決の種類は、以下の通り3種類あります。
取消訴訟の提起が認められる条件(訴訟要件)が厳しいため、却下される可能性も高くなります。
|
却下 |
取消訴訟を提起するための訴訟要件を満たさず、原告側の訴えが不適法だと認められる場合の決定です。 |
|
棄却 |
行政処分に違法性が確認されず、原告側の請求に理由がないため取消が認められない場合の判決です。 |
|
認容 |
行政側の違法性が認められ、処分または裁決の一部(あるいは全部)が取り消される場合の判決です。 |
行政庁から受けた処分や裁決によって不利益を被る具体的な内容について、以下で見ていきましょう。
行政庁からの処分で例を挙げると、税務処分があります。税務処分とは税務署長から受ける処分のことであり、
主に以上のような種類があります。処分対象が個人でなく企業の場合、億単位の加算税が発生することがあるため、処分理由が不当である場合には取消訴訟の検討が必要になるかもしれません。
また、公務員に関する懲戒処分も行政処分の一種であり、懲戒免職処分の理由に納得しない場合は取消訴訟を提起して国側と争う事例もあります。
裁決の取り消しを目的とする取消訴訟では、場合によっては行政処分との区別が難しいケースもありますが、当選を無効にされた議員が無効票を有効票にした裁決をめぐる訴訟が挙げられます。
それと、取消訴訟とは違う種類の訴えになりますが、参考までに無効確認訴訟についても説明すると、処分や裁決などの取り消しを求める訴えとは違い、処分や裁決の存否や効力の有無について確認することが目的になります。
上記の処分や裁決の取消訴訟とは異なり、行政処分(または裁決)の効力を確認するだけの訴訟であるため、実際に利用されるケースは少ないでしょう。
取消訴訟の役割と目的についてこれまで説明しましたが、行政処分を受けてすぐに取消訴訟を提起して裁判で争うことができるわけではなく、取消訴訟に至るまで以下のような不服申立ての手続きを取る必要があります。

再調査請求は、処分を行った原処分庁による再調査の見直し要求のことであり、任意で行う手続きになります。仮に再調査で棄却された場合でも、行政処分を行った理由が明確になるため、次段階の審理である審査請求で有効に働く可能性があります。
審査請求は行政処分の取消しを求めるためには必ず行う手続きであり、行政処分を受けてから3ヵ月以内(再調査の請求後の場合は1カ月以内)に審査請求書を提出する必要があります。
取消訴訟の一例として、以下の記事で課税処分の取消しを求めるための手続き方法と審査請求における審理方法について解説しているので、参考までにご確認いただければと思います。
審査請求の結果、却下や棄却が言い渡されても任意で再審査請求をすることが可能です。再審査請求の場合、審査請求の結果が通知されてから1カ月以内に手続きを行う必要があります。
上記で説明した通り、最低限でも審査請求をすれば取消訴訟の提起へと移行できますが、審査請求などの手続きと同様に、取消訴訟にも出訴期間が決められています。
基本的には、審査請求(または再審査請求)の結果が通知されてから6ヵ月以内(処分や裁決の事実を知らなかった場合でも1年以内)の出訴期間が設けられているため、なるべく早めに訴訟提起をするかどうか決めておいた方が良いでしょう。
行政不服審査制度を利用しても行政処分の取り消しが認められない場合、取消訴訟による裁判での争いになりますが、必ずしも訴えた側が勝てるとは限らず、むしろ行政事件では原告側である一般市民が不利になるケースが多いです。
その理由としては判断や基準が難しい訴訟要件があるので、以下で重要なポイントについて取り上げていきます。訴訟要件とは、取消訴訟の提起が妥当であることの条件です。
訴訟要件の中でも特に判断が難しいとされる処分性は、取消を要求する行政庁からの処分における『処分性』の有無が問われます。
参考までに処分性について定義された事例を挙げると以下の通り、一般市民側が行政行為によって何らかの不利益を被っていることが認められても、その行為がなされることによって法律上、個人の権利義務を形成し、または権利義務の範囲を確定することが認められない限り、処分性が無いとされて却下となります。
それ故、仮りに右設置行為によつて上告人らが所論のごとき不利益を被ることがあるとしても、右設置行為は、被上告人都が公権力の行使により直接上告人らの権利義務を形成し、またはその範囲を確定することを法律上認められている場合に該当するものということを得ず、原判決がこれをもつて行政事件訴訟特例法にいう「行政庁の処分」にあたらないからその無効確認を求める上告人らの本訴請求を不適法であるとしたことは、結局正当である。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、採用できない。
引用元:「裁判所」
原告適格とは、取消訴訟を提起する原告として認められるための基準であり、行政処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に認められます。
ポイントしては行政処分による利害関係の明確化であり、行政側との直接的な利害関係が証明されないと、法律上保護された利益を有する者として認めてもらえる可能性は低いと思われます。
それ以外にも取消訴訟の訴訟要件があり、以下表でまとめました。上記で説明した出訴期間のほか、訴訟を提起する場所(地方裁判所)の条件なども訴訟要件の一つになります。
取消訴訟の訴訟要件 |
|
要件1 |
処分性(処分の対象になるかどうか) |
要件2 |
原告適格(訴える者の資格) |
要件3 |
訴えの利益(取消訴訟によって回復する利益があるかどうか) |
要件4 |
裁判所管轄(訴訟を提起する場所の条件) |
要件5 |
出訴期間(訴訟を提起する時間的な制約) |
要件6 |
被告適格(訴えられる側の条件) |
最後に、取消訴訟で必要になる弁護士費用について確認していきましょう。訴訟要件や違法性の判断が非常に難しい行政事件においては、専門家である弁護士に相談するべきです。
取消訴訟に限らず審査請求などの不服申立て制度の利用を検討している場合、行政事件に携わっている弁護士に相談するのが良いでしょう。
初回相談を無料で対応してくれる法律事務所もあるので、取消訴訟で要する弁護士費用や裁判での勝ち目をあらかじめ聞いておくのが賢いやり方です。
あくまで一つの目安ですが、取消訴訟などの行政訴訟で弁護士に依頼した場合の弁護士費用について、以下表でまとめました。着手金は依頼時に支払う費用であるので、仮に原告側の請求が棄却されても依頼者側の負担金になります。
《着手金算出例》
|
経済的利益(裁判で請求する賠償額) |
着手金 |
|
300万円以下の場合 |
経済的利益 × 8% |
|
300万円を超え1,000万円以下の場合 |
経済的利益 × 5% +固定額 9万円 |
|
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 |
経済的利益 × 4% +固定額 20万円 |
|
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益 × 3% +固定額 69万円 |
|
3億円を超える場合 |
経済的利益 × 2% +固定額369万円 |
また、原告側の請求が容認されて行政処分が取り消された場合には報酬金を支払うことになりますが、報酬金の目安は着手金の2倍程度だとされています。
取消訴訟の提起で要求する経済的利益(損害賠償)の額によって弁護士費用は変わりますが、案件によっては300万円以上の高額な費用がかかります。
また、取消訴訟では裁判で1年~2年程度かかるため、費用だけでなく時間も相当かかります。そこまでの労力をかけてまで取消訴訟を提起するかどうかを決めるには、やはり弁護士の判断が必要になるでしょう。
弁護士に依頼すれば、行政処分の違法性を追及するための資料を準備できるほか、訴訟提起で提出する訴訟の書き方についてアドバイスをもらえるため、事務的な手続きの負担が軽くなります。
取消訴訟の役割と機能について説明しましたが、行政処分の取消請求は簡単に認容されないことがお分かりいただけたかと思います。
国や地方公共団体などの行政庁側と比較して、基本的に一般市民は弱い立場にあるので、裁判で争う場合には弁護士に相談して訴訟提起の準備を進めた方が良いでしょう。
|
取消訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


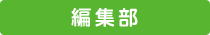
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。