決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


取消訴訟を提訴する際に提出する訴状(そじょう)は、裁判を起こす上で必要な書類になります。訴状には基本的に、処分を取り消す訴えである『請求の趣旨』と訴えを起こした経緯である『請求の原因』を明記することになります。
国や公共団体より下された処分や裁決は必ずしも確定事項ではなく、審査請求や取消訴訟を利用して取消しの請求をすることはできますが、今回は取消訴訟に関する訴状の書き方や提出時のポイントを確認していきたいと思います。
|
取消訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
行政事件訴訟の一種になる取消訴訟は民事訴訟の扱いになるため、提起するには裁判所へ訴状を提出する必要があります。訴状には決まったフォーマットはありませんが、記載すべき項目が決まっていますので記載例と合わせて説明していきます。
取消訴訟を起訴するために必要な書類である訴状は、審査請求を通さずに訴えを起こす場合と審査請求が通らず却下された後の場合で提出するタイミングが変わります。
訴訟での提起については下記の通り、民事訴訟法第133条で規定されています。
(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
引用元:「民事訴訟法 第133条」
民事訴訟法第133条を確認すると、『当事者及び法定代理人』『請求の趣旨』『請求の原因』の3つを訴状に記載する必要があることが分かります。それぞれの内容について順番に見ていきましょう。
当事者(原告と被告)と法定代理人は誰なのか通常は明確になっていますが、書類上の記載方法でいくつか注意点があります。下記表にて注意点をまとめました。
|
当事者(原告・被告)の表示における注意点 |
|
| 住所(所在地)の記載について | ・何丁目、何番地の丁目、番地等の記載について省略不可 例:○新宿区西新宿1丁目2番3号 ×新宿区西新宿1-2-3 |
| 原告又は被告が法人(株式会社,有限会社等)の場合の記載について | ・(株)(有)などの略称は使用不可 ・代表者名を記載する場合、代表取締役の記載の前に『代表者』と書くこと ・印鑑は会社の代表者印を使用すること |
| 原告又は被告が未成年の場合の記載について | ・未成年者の住所・氏名を記載すること ・その下の行に親権者(通常両親がいる場合は両親)の住所・氏名を記載すること ※原告又は被告が未成年の場合はその親権者(親)の戸籍謄本が1通必要 |
参照元:「裁判所 訴状作成上の注意事項」
取消訴訟を提起する側(訴える側)が裁判所の判決で何を求めるのか、といった主張内容が請求の趣旨に該当します。取消訴訟であれば例として、『受けた懲戒免職処分を取消しするために請求する』ことや『選挙の無効票を有効票にした裁決を取消しする目的で訴訟を提起する』訴えなどが考えられます。
また、取消訴訟を提起する原因は訴えられる側の被告にあると見なされるため、『訴訟費用は被告の負担とする』という要求も請求の趣旨に入るのが通常だとされています。
請求の趣旨に補足説明をするのが請求の原因であり、行政庁より処分や裁決を受けた経緯や取消を求める理由などを記載する項目になります。取消訴訟を提起した原因に関しては感情的な理由を書くのではなく、処分や裁決を取り消す必要がどうしてあるのかを論理的に説明することが求められるでしょう。
取消訴訟を提起する訴状の簡単なレイアウト例を以下で記載します。請求の趣旨や原因に加えて、証拠資料など訴状以外で添付している書類の内容も記載することになります。
《訴状 レイアウト例》
訴状の記載項目や書き方について上記で説明しましたが、取消訴訟を提起する原告側は提出方法や添付書類についても知っておくべきポイントがあります。それと訴状を提出する際には手数料がかかりますので、下記にて合わせて取り上げていきます。
※裁判所のホームページでも「民事訴訟事件手続案内」にて参照できます。
取消訴訟の原告または被告が法人である場合には『登記事項証明書』が必要になります。原則として3ヵ月以内に発行された原本を提出することが求められていますが、法務局や法務局出張所で取り寄せることが可能です。
訴状は1枚だけでは足らず、訴えられる側の被告の数+1部必要になります。被告が1人でも2部の訴状を提出する決まりになりますが、訴状を補足する証拠書類のコピー部数も同じく被告の数+1部を揃える必要があります。
裁判手続を利用する場合、手数料になる収入印紙を訴状に貼り付けることが定められています。手数料は訴訟の提起で請求する利益である訴額(そがく)に応じて決められますが、非財産権上の請求になる取消訴訟では一定の訴額(160万円)が決められています。
訴額に対する手数料について手数料額早見表で確認すると、160万の訴額(訴えの提起)では13,000円であることが分かります。
訴状と添付書類を送付する先は管轄下にある地方裁判所です。取消訴訟における訴訟要件(条件)の一つでもある裁判所管轄は、主に以下の基準で決められます。
《取消訴訟を提起する場所(裁判所)の管轄条件》
訴状を提出する先になる地方裁判所は、訴えられる側と訴える側の両方の所在地を基準に決められるとされています。
訴状を提出して取消訴訟を提起するタイミングについては、『審査請求』の選択を取らずに取消訴訟の提起に移行する場合(自由選択主義)と、審査請求の後であることが原則になる場合(不服申立前置主義)の2種類があります。
審査請求とは不服申立ての方法であり、裁判で争う前の段階で行政庁の処分について審査をしてもらうことになります。基本的には処分取り消しの訴えについて、審査請求の手段を取らなくても取消訴訟を提起することが可能だと法律上で規定されています。
第一節 取消訴訟
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
引用元:「行政事件訴訟法 第8条」
ただし、取消訴訟を提起するためには審査請求が必要になるケースもあります。例として公務員の場合は以下の通り、審査請求が却下されてからでないと取消訴訟の提起ができません。
(審査請求と訴訟との関係)
第九十二条の二 第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
引用元:「国家公務員法 第92条の2」
(審査請求と訴訟との関係)
第五十一条の二 第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
引用元:「地方公務員法 第51条の2」
公務員における取消訴訟では懲戒処分が関わってきます。
また、訴状を提出するタイミングに関連して、取消訴訟の提起(出訴)では一定の期間を超えてしまえば訴状を送っても却下されてしまいます。取消訴訟における具体的な出訴期間は下記表の通りです。
| 《審査請求をしなかった場合》 | 出訴期間 |
| 処分または裁決があったことを知った日から起算 | 6ヵ月 |
| 処分または裁決があった日から起算 | 1年 |
| 《審査請求をした場合》 | 出訴期間 |
| 審査裁決・決定を知った日から起算 | 6ヵ月 |
| 審査裁決・決定日から起算 | 1年 |
最後に取消訴訟の訴状を提出する場合に知っておくべき注意点を紹介します。取消訴訟は行政事件扱いになりますが、相談する相手は行政書士でなく弁護士にするべきでしょう。
訴状は裁判所に提出する書類になるため、原則としては弁護士や司法書士しか訴状を作成できません。具体的には弁護士法第72条で定められていますが、仮に行政書士に訴状作成の依頼をした場合は違法になるので、頼む場合は弁護士にしましょう。
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:「弁護士法 第72条」
訴状では立証が不足している場合は証拠書類も合わせて送付する必要がありますが、証拠書類の提出方法も決まりがありますので確認しておくべきでしょう。
証拠書類は原本でなくA4サイズのコピーで提出する必要があり、証拠書類の数に応じて1つずつ決まった番号の振り方もあります。
取消訴訟では専門的な知識がないと対応が難しいでしょう。訴状の記載方法のほかに、取消訴訟を提起して要望が通る可能性があるかどうかも事前に確認するべきです。行政事件を取り扱っている弁護士であれば、過去の事例などを参考に取消訴訟の妥当性などを判断してくれますので、取消訴訟を検討している場合は弁護士への相談をオススメします。
取消訴訟で必要になる訴状の書き方や提出方法について解説しましたが、法律的な知識が必要になりますので弁護士の力を借りながら訴状を確実に作成した方が良いでしょう。取消訴訟を提起しても処分や裁決が絶対に取り消される訳ではありませんが、納得がいかない問題であれば自身の主張を通すために取消訴訟の制度を利用するのも一つの手です。
|
取消訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


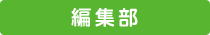
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。