
遺産相続
遺留分侵害額の計算方法|計算例や請求手続きも解説
2023.09.11
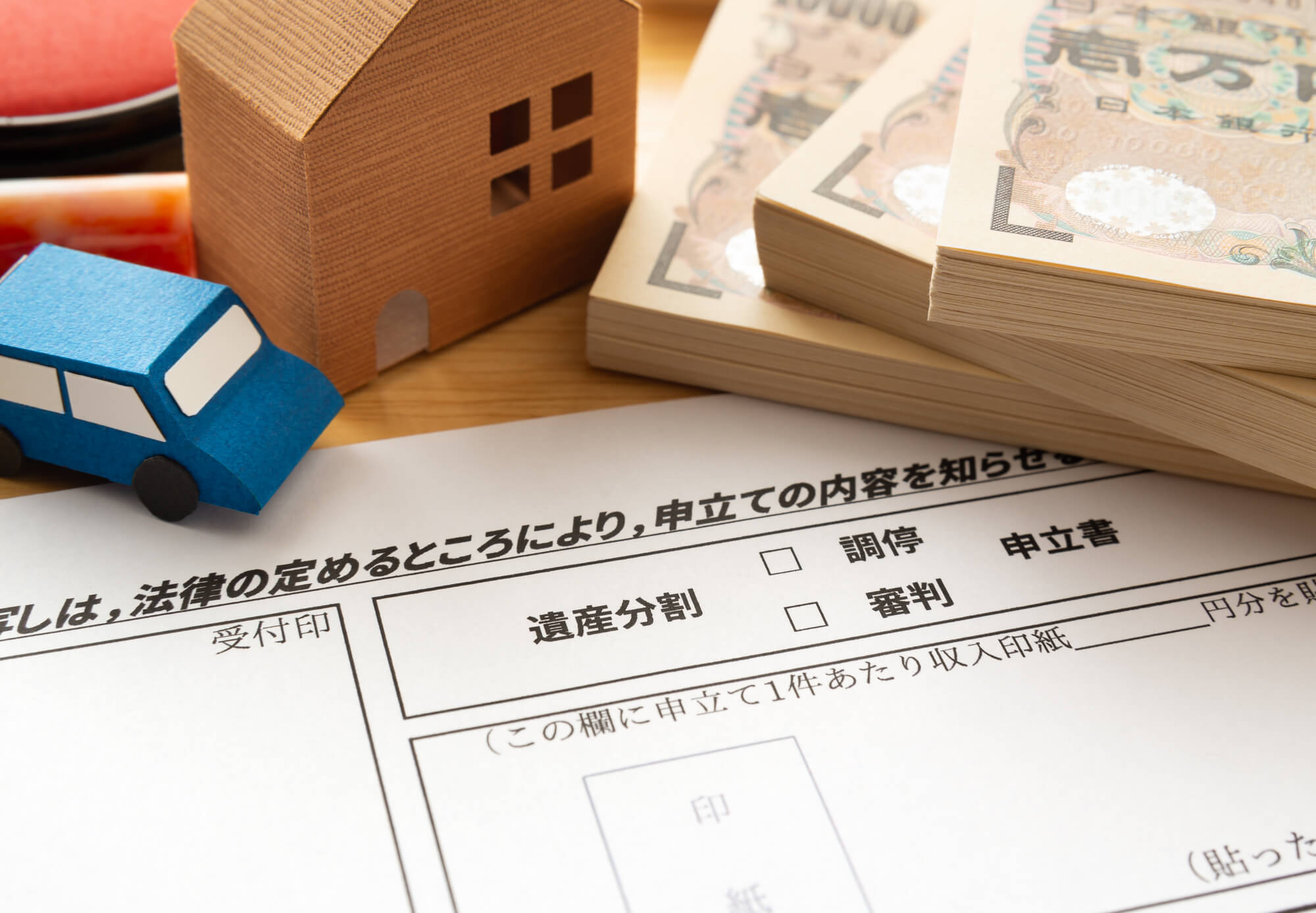
遺産相続手続きには、さまざまな期限が設けられています。
被相続人が亡くなって慌ただしい状況でも、着実に期限は迫ってくるので注意が必要です。
本記事では、「遺産相続の期限に間に合わないか不安だ」「相続人同士の意見がぶつかって遺産相続の話し合いが前に進まない」などの問題を抱えている方に向けて、以下の事項についてわかりやすく解説します。
特に、相続税に関する期限や年金・保険・不動産をめぐる手続き期限に間に合わないと、税制上のペナルティや刑事罰などを科されかねません。
早期に弁護士や税理士の知見を頼ることで、スムーズに遺産相続手続きを終わらせましょう。

遺産相続手続きは「期限の定めがある手続き」「期限の定めがない手続き」に分類されます。
まずは、期限の定めがある遺産相続手続き一覧を紹介します。
| 期限 | 手続き |
| 死亡を知ったときから7日以内 | 死亡診断書の受領、死亡届の提出 |
| 死亡日から14日以内 | 世帯主の変更届、年金・保険の手続き |
| 自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 | 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄) |
| 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内 | 準確定申告 |
| 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内 | 遺留分の侵害額の請求 |
| 死亡日の翌日から2年以内 | 死亡一時金の請求 |
| 相続により不動産の所有権を取得してから3年以内 | 相続登記(※2024年4月1日より施行) |
| 支払い事由が発生した日の翌日から3年以内 | 死亡保険金の請求 |
| 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 | 相続税の還付申告 |
被相続人が死亡した直後からさまざまな手続き期限が迫ってきます。
ご家族が亡くなって間もないころは気持ちの整理がつかない慌ただしい時期ですが、期限を迎える前に速やかに遺産相続に向けた手続きに着手しましょう。
「被相続人が死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときには、その事実を知った日から3ヵ月以内)」に、届出義務者が死亡届を役所に提出しなければいけません(戸籍法第86条第1項)。
なお、死亡届の提出は同居の親族、その他の同居人、家主・地主・家屋や土地の管理人に提出義務が発生します(戸籍法第87条第1項)
死亡届には、死亡診断書または検案書を添付する必要があります(戸籍法第86条第2項)。
死亡診断書は、被相続人が亡くなったあと、医療機関から交付されます。
また、火葬をおこなうためには市区町村長の許可を受ける必要があるので、死亡届の提出と同じタイミングで火葬許可申請書を提出するのが一般的です(墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項)。
なお、死亡届とは異なり、火葬許可申請書には法律上の提出期限は設けられていません。
被相続人が世帯主の場合、死亡によって世帯の変更があったときから14日以内に、世帯がある住所地の市区町村長宛てに変更届を提出する必要があります(住民基本台帳法第25条)。
ただし、世帯に残った人が1人だけで世帯主が客観的に明らかなときには、世帯主の変更届の提出手続きは不要です。
被相続人が国民年金を受給していた場合、「死亡してから14日以内」に年金の受給停止手続きをおこなう必要があります(、国民年金法施行規則第24条第1項)。
受給権者死亡届(報告書)などの必要書類の詳細については、「ねんきんダイヤル」もしくは年金事務所にお問い合わせください。
被相続人が厚生年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きの期限は死亡してから10日以内である点には注意が必要です。
なお、国民年金・厚生年金のどちらも、日本年金機構にマイナンバー情報が登録されている場合には、受給停止手続きを省略できます。
国民健康保険の被保険者資格者が死亡したとき、後期高齢者医療制度利用者が死亡したとき、介護保険の被保険者が死亡したときには、それぞれ保険証の返還手続きが必要です。
国民健康保険の被保険者については死亡してから14日以内、会社員などの被雇用保険の被保険者については死亡してから5日以内というように、保険証の返還期限が異なる点には注意が必要です。
次に、被相続人が死亡した直後ではないものの、期限に注意を要する遺産相続手続きについて解説します。
葬儀や四十九日、自宅の片付けなどで奔走する時期ですが、期限を徒過しないように時間に余裕があるタイミングを見計らって手続きを進めましょう。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択するのかを決定しなければいけません(民法第915条第1項)。
まず、相続開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認・相続放棄の手続きを履践しない場合、単純承認を選択したと扱われます(民法第921条第2号)。
つまり、単純承認をするときに特別な遺産相続手続きは必要ないということです。
次に、限定承認及び相続放棄のどちらを選択するとしても、3ヵ月以内に家庭裁判所に対して必要書類を提出して、限定承認もしくは相続放棄をする旨について申述しなければいけません(民法第924条、第938条)。
被相続人が死亡した場合、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した故人の所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に所得税の申告と納税をしなければいけません(所得税法第124条、第125条)。
この一連の手続きを、準確定申告といいます。
このとき、被相続人に申告すべき所得がない場合は準確定申告の手続きは不要です。
準確定申告書および付表(相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などの必要事項の記載が必要)を、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告および納付手続きをおこなわなければいけません(相続税法第27条第1項、第33条)。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した相続人の住所地を所轄する税務署ではないのでご注意ください。
相続税の課税対象になる財産として、以下のものが挙げられます。
相続税の申告額が不足していた場合、過少申告加算税が加算されることがあります。
遺産の内訳が複雑な場合や高額な場合には、弁護士や税理士のサポートを受けることをおすすめします。
また、想像以上に相続税額が高額になって申告期限までに相続税額を用意できないとしても、税務署の連絡をしないまま期限を徒過してはいけません。
相続税の納付期限に間に合わないときには、延納制度による分割払いや物納制度での支払いを検討しましょう。
なお、延納制度を利用するには、以下全ての要件を満たす必要があります。
遺留分とは、一定範囲の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
そして、被相続人が遺留分権利者以外に財産を贈与・遺贈したことが原因で、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、贈与・遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害された金額相当額の支払いを請求できます(民法第1046条第1項)。
「相続が開始したことおよび遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内」「相続開始の時から10年以内」に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、遺留分を侵害された金額を取り戻すことができなくなります(民法第1048条)。
相手方に配達証明付内容証明郵便を送付して誠実な対応を期待できないときには、遺留分侵害額の請求について調停などを申し立てる必要があるので注意しましょう。
死亡一時金とは、死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を36ヵ月以上納付した人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに死亡したときに、被相続人と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子ども・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されるものです(国民年金法第52条の2)。
保険料を納付した月数に応じて、120,000円~320,000円(付加保険料を納めた期間が36ヵ月以上なら8,500円加算)が支給されます。
死亡一時金の請求権は、「権利を行使できるとき(死亡日の翌日)から2年以内」に所定の手続きを踏まなければ消滅時効にかかります(国民年金法第102条第4項)。
詳細については、お住まい地域の自治体や年金事務所までお問い合わせください。
死亡保険金とは、加入者である被保険者が何かしらの理由で死亡したときに、遺族などに対して支払われる生命保険金のことです。
死亡保険金の受け取り期限は多くの場合、支払い事由が発生した日の翌日から3年に指定されています。
被保険者死亡後に生じた事情次第では期限経過後に受け取ることもできますが、手続きが煩雑になるので必ず3年以内に死亡保険金を請求しましょう。
2024年4月1日から、所有者不明等の土地への対策を目的として、新しい不動産登記制度がスタートします。
これにより、相続によって不動産を取得した相続人には相続登記の申請義務が課されることになり、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請手続きを履践しなければいけなくなります。
正当な理由がないのにもかかわらず相続登記の申請義務を懈怠したときには、10万円以下の過料が科されます。
なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間を与えられているだけで、相続登記の申告義務化が適用されます。
過去に不動産を相続したにもかかわらず登記手続きを適正に履践していなければ、罰則の対象になるので注意しましょう。
相続税を払い過ぎたとき、相続税の還付申告をすればお金が戻ってきます。
還付申告の期限は、相続税の申告期限から5年以内と定められています(国税通則法第23条)。
つまり、相続税の過払いについては被相続人が死亡した日の翌日から5年10ヵ月以内に更生の請求を履践しなければいけないということです。
相続税の過払いが発生しやすい事例として、以下のようなケースが挙げられます。
遺産相続手続きの中には、期限の定めがないものも存在します。
ただし、これを理由にいつまでも先延ばしにしていると、いざ手続きに着手した段階で準備に思いがけず手間取る可能性があります。
そのため、できるだけ早いタイミングで済ませるようにしましょう。
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。
遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをおこないます(民法第1004条)。
遺言書の検認自体には時効や期限はないものの、相続にともなう諸手続き時効・期限までに終わらせるためにも、遺言書を発見した際には早めに検認することをおすすめします。
被相続人の死亡により相続が発生したときには、「誰が、何を相続するのか」を判断するために、相続人調査・相続財産調査が不可欠です。
仮に遺言書が残されていたとしても、遺言書に全財産の行く末が記載されているとは限りません。
相続人調査・相続財産調査自体には手続き期限は設けられていません。
しかし、単純承認・限定承認・相続放棄の判断は「相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」にしなければいけないことを踏まえると、それまでに相続人調査・相続財産調査を終える必要があります。
相続人調査・相続財産調査は、以下のようにさまざまな手続きが必要です。
短期間で間違いなく調査を終えるには、相続問題に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
| 相続人調査で必要な作業 | ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票の取り寄せ ・相続人の連絡先の入手 ・各相続人に対して遺産相続について問い合わせ |
| 相続財産調査で必要な作業 | ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・戸籍全部事項証明、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書、相続人の身分証明書の取り寄せ ・不動産の売買契約書、登記、納税通知書の確認および取得 ・金融機関や証券会社に対する開示請求 ・個人信用情報機関(CIC・KSC・JICC)への開示請求で債務状況の調査 ・その他被相続人の所有財産を全て調査して財産目録を作成 |
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺産の分割方法などについて話し合う手続きのことです。
相続人同士の話し合いがまとまらないときには、裁判所を利用して調停・審判という形で遺産の配分方法の決着を目指します(民法第907条)。
遺産分割協議自体の期限は、決まっていません。
ただし、相続税の支払い期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
期限内に遺産分割協議を終わらせて、各相続人への遺産配分を終わらせるようにしましょう。
万が一、遺産分割協議がまとまらず未分割のまま相続税の申告をする際は、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。
分割見込書を提出することで、遺産分割の確定後に修正申告をする際、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を適用することができます。
また、2021年4月1日に施行された改正民法で相続開始から10年が経過したあとに遺産分割をすると、特別受益や寄与分は考慮されず、法定相続分や指定寄与分によっておこなわれることになりました(民法第904条の3)。
そのため、特別受益や寄与分を主張して不利益を避けたいのであれば、相続開始から10年以内に遺産分割協議・調停・審判をおこないましょう。
被相続人名義の銀行口座の名義変更・解約手続きも、とくに期限は定められていません。
ですが、被相続人名義の預貯金口座は早めに金融機関に連絡を入れて凍結手続きを進めるのが無難です。
これは、被相続人死亡後にキャッシュカードや通帳を使って相続人が勝手にお金を引き出してしまうと、単純承認をしたと見なされる可能性があるためです。
葬儀費用の支払いなどで口座のお金を使用したい場合、「相続預金の払い戻し制度」を利用できることがあります。
なお、凍結された被相続人の預貯金口座は、遺産分割協議が終了した時点で解除してもらえます。
遺品整理や形見分けにも期限は設けられていません。
葬儀が終わって落ち着いたタイミングなど、家族・親族などの気持ちを整理しやすい時期を見計らっておこないましょう。
ただし、被相続人が賃貸物件に居住しており、死亡後に物件を引き払う場合には明け渡しまでに遺品整理・形見分けをする必要があります。
その際、思い出の品を数人だけの判断で形見分け・処分すると、話し合いに参加できなかった家族・親族との間に禍根を残しかねません。
誰が何を引き取るのかについて、ある程度のコミュニケーションの機会はもつべきでしょう。
さらに、高額なアクセサリーなどについて形見分けをしたときには、相続税も発生します。
そのため、特に高額の遺品については取扱いに注意してください。
遺産相続手続きの中には、期限に間に合わなかったときにペナルティが生じるものがあります。
期限さえ遵守すればペナルティは回避できるので、被相続人が亡くなったあと、落ち着いたタイミングで必ず各手続きを進めましょう。
遺産相続手続きの期限に間に合わなければ、過料などの行政罰や刑事罰を科される場合があります。
まず、正当な理由なく死亡届の提出期限を徒過すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(戸籍法第37条)。
次に、世帯主変更届の届出が正当な理由がないのにもかかわらず遅れたときには、5万円以下の過料が科される可能性があります(住民基本台帳法第52条第2項)。
さらに、正当な理由がないのに年金の受給権者死亡届の提出が遅れたときには、10万円以下の過料が定められています(国民年金法第114条)。
また、受給権者死亡届の提出が遅れただけではなく、偽りその他不正な手段によって年金を不正受給したケースでは、3年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑が科されることがあります(国民年金法第111条)。
さらに、より重い詐欺罪が成立した場合には「10年以下の懲役」が科されます(刑法第246条第1項)。
相続税の申告・納付期限に間に合わずに遅れてしまった場合、本来の相続税額に加えて附帯税の支払い義務も生じます。
相続税の附帯税は、加算税と延滞税に分類されます。
相続税にはさまざまな特例制度・軽減制度が設けられています。
これらの税制上の優遇制度を活用すれば、高額になりがちな相続税の支払い額を大幅に軽減できます。
しかし、相続税の申告・納付期限を遵守しなければ、各種特例制度の適用を受けることができません。
相続税については以下の特例制度が定められているので、期限内に申請手続きをおこないましょう。
「遺産相続の期限を守りたい」「相続人同士で揉め事が起きて期限を守れないか不安だ」という方のために、遺産相続の期限を守るための4つのコツについて解説します。
家族・親族関係がうまくいっていないために、遺産相続の話し合いがなかなか進まないケースが多くあります。
遺産分割協議などをスムーズにおこなえないと、調停・審判手続きの利用を強いられたり、相続税の申告・納付期限に間に合わないという事態に陥りかねません。
ですから、相続人同士で話し合いをするときには、可能な限り感情を抑えて冷静でいることを意識しましょう。
遺産相続を円滑に進めるには、全ての相続人の意見を上手に擦り合わせる必要があります。
あなたの主張だけを押し通すのではなく、他の相続人の意見・要求もしっかりと確認をして、現実的な妥協点を探しましょう。
相続人が遺産相続について間違った知識を有していると、遺産相続に関する話し合いが円滑に進みません。
相続分や遺留分の割合、遺産分割協議や調停・審判の流れ、相続税の申告期限など、最低限の法的知識は正確に理解しておくことをおすすめします。
遺産相続は、相続人だけではなく各相続人の家族なども巻き込んだ揉めごとに発展しかねない問題です。
けんか腰で感情的になってしまうと、遺産相続手続きが期限に間に合わず、結果として全ての相続人に不利益が生じかねません。
そこで、遺産相続をスムーズに進めるには、最初から相続問題に強い弁護士の力を借りることをおすすめします。
専門的な知識を有する弁護士が第三者の立場から争点を整理して相続に必要な手続きを代理してくれるので、遺産相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。
ベンナビ相続では、遺産相続問題を得意とする法律事務所を多数掲載しています。
お住まい地域や被相続人の所在地からアクセスの良い事務所をご検索のうえ、信頼できる弁護士までお問い合わせください。
最後に、遺産相続手続きの期限に関して寄せられるよくある質問をQ&A形式で紹介します。
公共料金の契約者が死亡して誰も使用しないときには解約手続きが必要です。
もし誰かが継続使用するなら名義変更で済みます。
公共料金の解約手続きに期限は設けられていません。
しかし、解約手続きが遅れるほど公共料金の費用は毎月発生し続ける点に注意が必要です。
また、被相続人名義の口座から公共料金を引き落としていると、口座が凍結されて滞納状態に陥りかねません。
期限が設けられていないとはいえ、公共料金の解約手続きはできるだけ速やかにおこないましょう。
まず、被相続人が死亡しても、被相続人の運転免許証を返納する必要はありません。
ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合、運転免許証更新連絡書等の通知が郵送され続けることになります。
これらの通知の停止を希望するなら、最寄りの警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場までお問い合わせのうえ、所定の手続きをおこなってください(手数料は無料)。
次に、被相続人のパスポートは、名義人の死亡によって効力を失います(旅券法第18条第1項第1号)。
最寄りの都道府県の申請窓口、在外公館に届け出たうえで失効手続きが必要です。
自動車やバイクを相続した場合、「所有者の変更があった日から15日以内」に移転登録の申請(名義変更)をする必要があります(道路運送車両法第13条第1項)。
移転登録の申請については、期限を過ぎたとしても罰則は存在しません。
そのため、遺産相続手続きが終わって自動車やバイクの相続人が確定するまで数ヵ月を要したとしても、法律上のペナルティを科されることはないでしょう。
ただし、名義変更手続きを怠ったままでは相続人自身の所有物とは認められないので、一時抹消登録や永久抹消登録ができなかったり、交通事故を起こしたときに保険が支払われないなどの可能性もあります。
自動車やバイクを相続して使用する場合には、できるだけ速やかに移転登録の申請を済ませておくことをおすすめします。
遺産相続の各手続きには厳格な期限が設けられているものがあります。
特に相続税の申告・納付期限に遅れると、追徴によって高額の経済的負担を強いられる危険性があるので注意が必要です。
期限内に遺産相続を終わらせるには、弁護士や税理士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「ベンナビ相続」では遺産相続問題全般に強い弁護士を多数掲載中ですので、初回無料相談などの機会をぜひご活用ください。
