決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
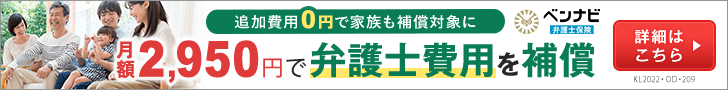
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、『仕事の方法や進め方を労働者の裁量にゆだねる』制度です。具体的には『好きな時間に出勤し、好きな時間に退勤できるが、一日何時間働いても一定の時間働いたものとみなす』制度で、適用できる職種は法律で明記されています。
『自由で柔軟な働き方ができる』というのがこの制度の魅力ですが、『合法的残業代カット』や、『定額働かせ放題』などと呼ばれているのも事実です。
この記事では、今話題の裁量労働制について説明していきます。
目次
まずは裁量労働制の特徴についてわかりやすく説明していきます。
裁量労働制は、『実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた労働時間分働いたとみなす』制度です。
1日のみなし労働時間が8時間の場合、『その日に5時間働いても、10時間働いても、8時間働いたとみなす』というのが最大の特徴です。
裁量労働制のもとで働く場合、定時という決まりに縛られることがなくなります。自分の好きな時間に出勤し、好きな時間に退勤することが可能です。
フレックスタイム制と同じなのではないかと感じる人もいるでしょう。両者は出退勤時間を労働者が決めることができるという点で似ていますが、まったくの別物。労働時間の計算方法が異なっているのです。
フレックスタイム制の場合は、実労働時間を月ごとに集計し、実労働時間を踏まえて残業代が支払われます。
裁量労働制の場合は、実労働時間ではなくみなし労働時間によって労働時間が集計されますので、実労働時間が長かろうと短かろうと、賃金が変わることはありません。
みなし残業制度は残業時間にかかわらず一定時間を残業したものとみなして固定の割増賃金を支払う制度です。
残業時間によらず、一定の賃金を支払うという点で、裁量労働制に類似しているように見えますが、みなし残業制度の場合、みなし残業時間を超える残業をした場合には、超過分について別途精算が必要です。
裁量労働制の場合、そもそも実労働時間によって賃金や割増賃金が算定されませんので、この点が根本的に違います。
裁量労働制はどんな仕事にも適用できるわけではありません。ここでは裁量労働制の種類と適用できる仕事を紹介します。
業務の性質上、『やり方や時間配分を労働者にゆだねてしまった方がよい仕事』に対して専門業務型裁量労働制を適用できます。具体的には、下記の仕事に適用できます。
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析又は設計の業務
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は番組の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
【引用元:専門業務型裁量労働制の適正な導入のために – 厚生労働省】
本社や本店など、会社において重要な場所で、『企画・立案・調査や分析』などの仕事をしている場合には企画業務型裁量労働制を適用できます。
企画業務型裁量労働制は適用にあたり、労使委員会を設置し、5分の4以上の賛成を得る、労働者の同意を得るといった手続が必要となります。
裁量労働制を導入するには、使用者と労働者が協定を結ぶ必要があります(労使協定)。使用者の一方的な判断で導入してしまうと、残業代の削減などのために悪用されてしまう可能性があるからです。
協定で定めなければいけないことは、
などが代表的です。
裁量労働制を導入することでうまれるメリットについて説明します。
『好きな時間に出勤して、好きな時間に帰っていい』これは裁量労働制の最大の特徴であり、メリット。有効活用することができれば、子育てや介護、闘病などそれぞれの事情に合わせた柔軟な働き方ができます。
趣味がとにかく大切な人であれば、『趣味のゴルフをする日は夕方出勤、それ以外の日は午前から出勤』なんていうのも裁量労働制であれば可能になります。
1日何時間、毎月何時間働かなければいけないというルールはなく、『成果をあげてくれれば何でもいい』のが裁量労働制です。仮に他の人に比べて2倍のスピードで仕事をこなせるのであれば、労働時間は半分で済ませることができます。
既存のルールだと、残業時間が長い人ほど残業代が多く支払われることになります。それにより、
といった問題を抱えていました。ですが、裁量労働制の場合、残業代は出ず、仕事が終わった人から帰宅することになります。
その状況になれば、それぞれが仕事を本気でやるようになり、効率よく進めるにはどうしたらいいかを考えるようになります。結果として会社の労働生産性があがるでしょう。
そんな裁量労働制にもデメリットがあります。
裁量労働制を導入することで、残業代は発生しなくなってしまいます。
システム上仕方ないのですが、このようなデメリットがあります。
労働者が長時間働いても、会社は決められた賃金以外を支払う義務はありません。会社に制度を悪用されてしまった場合、『定額働かせ放題』のような状態になってしまい、労働者が常に長時間労働を余儀なくされてしまう可能性は否定できません。
裁量労働制は、『仕事の方法や進め方を労働者にゆだねてしまう』制度です。この制度が導入された場合、労働者は自由に仕事を進めることができる代わりに、実労働時間に関係なく一定の時間働いたものとみなされます。
適切に利用されれば労働者にも使用者にも大きなメリットがある反面、悪用されてしまった場合には実労働時間が長くなった上に残業代がでないという最悪の状況になります。
導入にあたっては労使協定を結ぶ必要があるため、自身の職場で導入が検討されている場合は、使用者(企業側)と事前にしっかり話し合っておくのがおすすめです。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
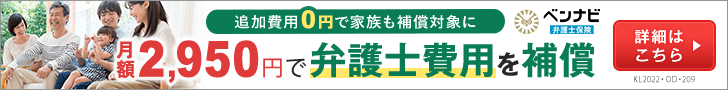
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037


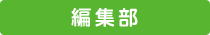
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。